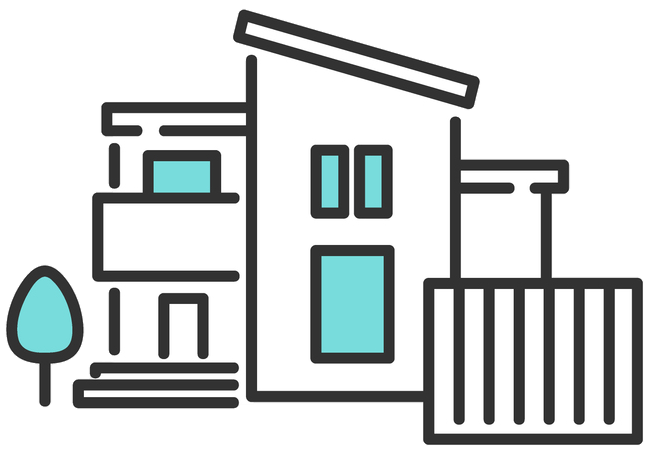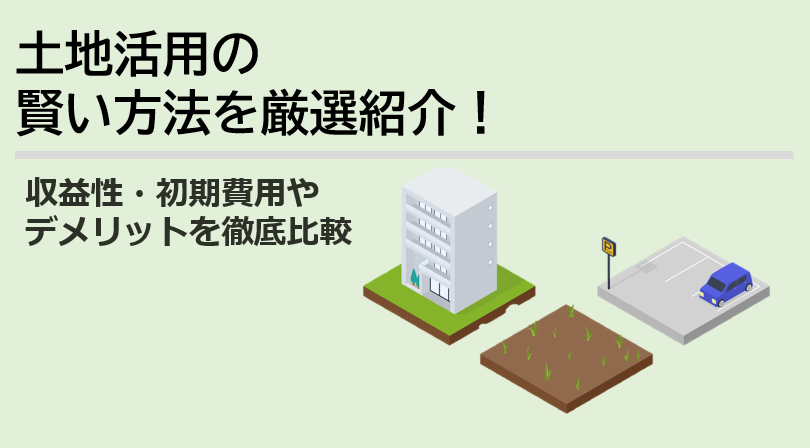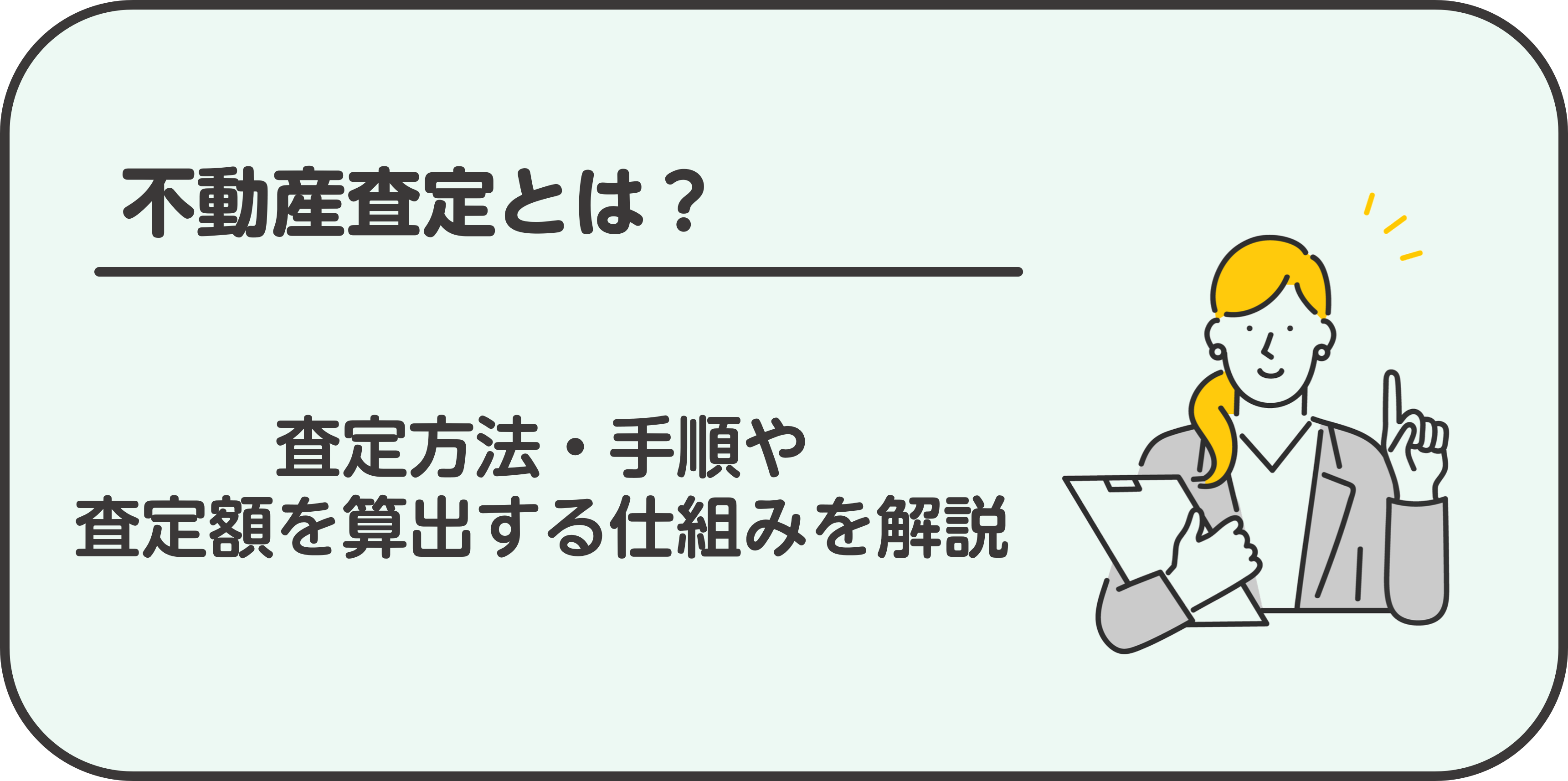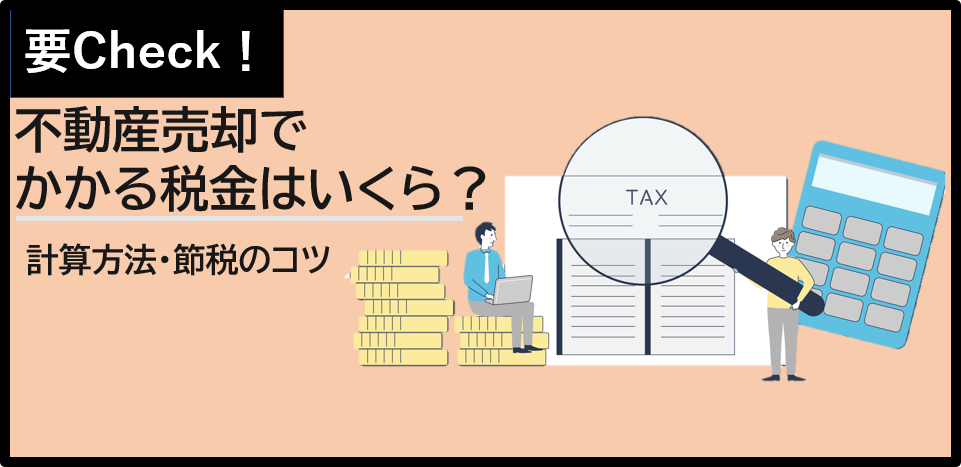
- 本ページにはPRリンクが含まれます。
-
当サイトでは、アフィリエイトプログラムを利用し各事業者から委託を受け広告収益を得て運営しております。
不動産売却は、不動産を売る事で、丸々利益が入るだけではありません。さまざまな税金が課されるので、トータルすると物件を売ったのに損をしてしまうこともあります。
また、不動産売却にかかる税金は、支払いのタイミングや額が決まっているものもありますが、中には売却額によって発生の有無や、課税額が決まるものもあるので、注意が必要です。
戸建て住宅やマンション・アパートなどの不動産を売却すると、以下5種類の税金が発生します。
| 税金 |
納付時期 |
納付方法 |
| 印紙税 |
売買契約を締結したとき |
収入印紙購入後、契約書に貼付、消印を持って納付完了 |
| 抵当権抹消登記 |
不動産についている抵当権の抹消登記などで発生 |
収入印紙を使用して納付
登記費用として司法書士に支払い、代金を貰った司法書士が代わりに納付する |
| 譲渡所得税 |
売却した不動産を引き渡した翌年の確定申告後 |
確定申告提出後、納付書を添えることで納付が完了 |
| 住民税 |
売却した不動産を引き渡した翌年の確定申告後 |
給与所得者は確定申告を提出することで納付が完了
普通徴収の方は確定申告提出後、別途納付書を作成・提出を持って納付完了 |
| 復興特別所得税 |
所得税中に含まれている |
確定申告提出後、納付書を添えることで納付が完了 |
特に、不動産引き渡し後に課される譲渡所得税は、売却額、物件を所有していた期間によって変化するので、仕組みを事前に知っておく事をお薦めします。
この記事では、不動産売却にかかる税金のうち、利益に対して課される譲渡所得税について詳しく解説していきます。
→不動産売却の方法とは?不動産を売るなら読むべき鉄則!成功した人の共通点
この記事の監修
叶税理士法人 東京事務所代表
税理士・上級相続カウンセラー
大学卒業後は、英会話教材を飛び込み営業により訪問販売しておりましたが、一生働ける仕事をしたいと思い税理士を目指しました。
不動産投資に特化した税理士事務所で働きながら、沢山の収益物件について税務と投資の面で多くの知識を得られたことを活かし、自分でも不動産投資を始めました。
現在では、札幌や北陸を中心に5棟の物件を保有しつつ、不動産投資家さんの気持ちがわかる税理士になるよう日々勉強し、色々な情報を集めています。
譲渡所得税の仕組みと計算式
不動産の売買契約が成立すると、まず仲介手数料(→不動産売却における仲介手数料の金額と必要性)が発生しますが、引き渡しを行ったあとに、譲渡所得税が新たに課税されます。
譲渡所得税とは、不動産売却で利益が出た際に、所得税と住民税に上乗せで課される税金の通称です。
課される譲渡所得税は決まった計算式で算出されるので、式さえしっていれば、売却前でも今の自分の手持ち額と不動産の予想売却額を合わせたシミュレーションが可能です。
譲渡所得税の計算式
譲渡所得税の計算式
譲渡所得税=税率×{譲渡価格-(取得費+売却費用) }
譲渡所得税の計算式は、以上の通りです。
取得費は、不動産の購入代金と取得に要した費用の合計額(家の場合は減価償却費を差し引く)と譲渡収入金額の5%のうち、大きい額の方が採用されます。
売却費用とは、仲介手数料、登録免許税など、売却の為にかかった経費の合計のことです。
また、実際に課税される額は、この譲渡所得から特別控除を引いたものとなります。
譲渡所得税は所得税と住民税に上乗せされますが、どちらの場合も計算式は同じです。
ただ、それぞれの税率が異なるので、金額に違いが出ます。
譲渡所得税の税率
| 税区分 |
不動産の所有期間 |
所得税※ |
住民税 |
| 短期譲渡所得 |
5年未満 |
30.63% |
9% |
| 長期譲渡所得 |
5年以上 |
15.315% |
5% |
※所得税に復興特別所得税2.1%を上乗せ
不動産売却でかかる譲渡所得の税率は、短期(不動産所有期間が5年以下)と長期(5年超)で、以上のような違いが出ます。
この際の注意点として、所有期間は不動産の購入日から引渡日までを数えるのではなく、引き渡した年の1月1日までとなります。
多くの人が勘違いをしている所ですが、これを間違えると無駄に高い税金を納めなければなりません。
不動産売却を始めてしまったあとでは、期間調整で税率を下げるのは難しいので、事前の調整が必要です。
所有期間10年超の特例
所有期間が5年を過ぎた不動産を売却すると税率が下がりますが、10年を過ぎると特例が適用され、更に税率が引き下げられます。
| 税区分 |
不動産の所有期間 |
課税譲渡所得 |
所得税※ |
住民税 |
| 長期譲渡所得 |
10年以上 |
6,000万円以下 |
10.21% |
4% |
| 6,000万円以上 |
15.315% |
5% |
※所得税に復興特別所得税2.1%を上乗せ
この際、6,000万円以下の部分の適用税率は所得税が10.21%、住民税が4%となります。
特別控除を受けた後に残った譲渡所得が6,000万円以下であれば、この税率が丸々適用されます。
もしも、譲渡所得が6,000万円を超える場合は、6,000万円分はこの税率が適用され、余剰分は長期譲渡所得の税率が適用されます。
譲渡所得税の具体的な計算方法
前述の通り、不動産売却にかかる譲渡所得税は、以下の計算式で求めることができます。
譲渡所得税の計算式
譲渡所得税=税率×{譲渡価格-(取得費+売却費用) }
該当する数字をこちらの計算式に当てはめれば良いのですが、各項目を算出する際も少し手間がかかります。
ここからは、不動産売却にかかる税金の計算方法を、初心者にもわかりやすく流れに沿って解説していきます。
Step1.譲渡所得(不動産売却で発生した利益)を計算する
譲渡所得税は不動産売却で発生した利益に対して課されるので、まずはこの利益(譲渡所得)を求める必要があります。
譲渡所得は、以下の計算式で求めます。
譲渡所得の求め方
譲渡所得=収入金額(売却代金)-取得費(購入代金+諸費用-減価償却費)-譲渡費用(売却時にかかった諸経費)-特別控除額
それぞれの項目の意味を確かめていきましょう。
収入金額には固定資産税の精算金も含まれる
収入金額とは、そのまま不動産売却で得た収入のことです。
収入金額は売買契約時に手付金、引き渡し時に残金という形で、2回に分けて支払われます。
収入金額はこの2回に分けて支払われた金額を合計したものになります。
また、1年の途中で不動産を売却した時は、払いすぎている固定資産税を買主に払い戻してもらいます。
こちらの金額(固定資産税の精算金)も収入金額へ含むようになります。
取得費を計算する
取得費は不動産の取得にかかった費用のことで、購入代金の他にも以下の経費を計上することができます。
取得費にできる費用一覧
- 設計変更費用
- 増改築リフォーム費用
- 仲介手数料
- 不動産取得税
- 登録免許税や登記手数料
- 契約書の印紙代
- ローン事務手数料
- ローン保証事務手数料
- 固定資産税・都市計画税の精算金
- 抵当権設定の登録免許税や登記手数料
- 建物に付属する設備費
- 建築費や工事にかかった諸費用
- ローン借入日~所有開始までにかかったローン金利
- ローン借入日~所有開始までにかかったローン保証料
- ローン借入日~所有開始までにかかった団体信用生命保険料
取得費の計算は他の項目に比べて少し難しいので、後ほど詳しく説明します。
売却費用(譲渡費用)を計算する
売却費用(譲渡費用)とは、不動産を売却する際に支払った関連費用のことです。
売却費用には、以下のようなものが含まれます。
- 仲介手数料
- 印紙代
- 立退料
- 取り壊し費用
- 売買契約の違約金
- 登録免許税
ただ、不動産売却の流れは人によっても異なるので、売却費用として計上できるか不明なものもあるかと思います。
この時は遠慮なく不動産会社に相談しましょう。
特別控除額を計算する
ここまでの計算で収入金額と取得費、譲渡費用の3点を求めることができたら、譲渡所得がいくらになるのかが求められます。
譲渡所得を求めたら、最終的に収める譲渡所得税がいくらになるのかを求めるだけです。
しかし、譲渡所得税には、税金の軽減措置として特別控除が用意されています。
中でも3,000万円の特別控除を活用すれば、最終的に収める税金の負担軽減が図れるだけじゃなく、金額によっては譲渡所得税の納付が免除されます。
免除されるケースは、特別控除額を除いた譲渡所得が3,000万円を下回った時です。
例えば、譲渡所得が2,900万円の時に3,000万円の特別控除を活用すれば、最終的に残る譲渡所得は-100万円となり、譲渡所得税の納税が免除されます。
なお、特別控除を利用するには、所定の条件を満たしておくことと、確定申告を提出しなければ利用できません。
Step2.税率を計算する
譲渡所得を求めたら、次にかかる税率を計算します。
税率は前述の通り、所有期間が5年以内か5年超かによって変わることを覚えておけばOKです。
ただ、所有期間は注意が必要で、取得した日から引き渡した年の1月1日までの期間を計算するようになります。
2015年4月1日~2020年5月1日までの経過年月は素直に計算すると5年1か月です。
ただ、これを所有期間に当てはめると2015年4月1日~2020年1月1日=4年9か月となり、税金が減額されません。
とはいえ、あえて所有期間を数年延長して長期譲渡所得を狙うようなことはおすすめできません。
基本的には早く売ったほうが築浅のうちに売却できるので、余裕を持って税金の納付が可能になります。
不動産売却の取得費の計算方法
不動産売却の税金を計算するには、取得費の計算が重要になります。
前節で紹介した「譲渡所得」を求めるために計算する取得費は、不動産の購入価格から減価償却を差し引くことで求められます。
また減価償却は、時間が経つにつれて劣化していく資産に対して使用するものです。
つまり、アパートやマンション、戸建て住宅など、時間が経つにつれてほころびが観られる資産に対して使用ができ、時間が経っても劣化が観られない土地に対しては使用できません。
アパートやマンション、戸建て住宅などに減価償却が使用できるのは築年数という概念があるからです。
この減価償却費を求めるときは、以下の計算式を活用して計算していきます。
減価償却費の求め方
減価償却費=建物の取得費(購入費)×0.9×(法的耐用年数の1.5倍の年数の償却率)×経過年数※
※経過年数の6ヶ月以上の端数は1年とし、6ヶ月未満は端数切り捨てで計算する
上記式中の「法的耐用年数の1.5倍の年数の償却率」は、以下の表を参考にすることで求められます。
| 建材 |
法的耐用年数 |
法的耐用年数×1.5 |
償却率 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート造もしくは鉄筋コンクリート造 |
47 |
70 |
0.015% |
| れんが造、石造又はブロック造 |
38 |
57 |
0.018% |
金属造
※骨格の肉厚が4mmを超える |
34 |
51 |
0.02% |
金属造
※骨格の肉厚が3mmを超え4mm以下 |
27 |
40 |
0.025% |
金属造
※骨格の肉厚が3mm以下 |
19 |
28 |
0.036% |
| 木造もしくは合成樹脂 |
22 |
33 |
0.031% |
| 木造モルタル造 |
20 |
30 |
0.034% |
取得費に計上できる経費を整理する
まずは、取得費計上が可能な経費を洗い出しましょう。
取得費計上ができる経費はあくまで取得(購入)にかかったものであり、その後の運用のために支払われた管理費や住宅ローンの返済費用などは計上できないので注意しましょう。
取得費の減価償却費を計算する
取得費の減価償却費を計算する方法は、定額法と定率法の2種類があります。
定額法は毎年一定の金額を減価償却する方法で、定率法は一定の割合で減価償却費を求める方法です。
例えば、取得費が2,000万円の不動産を4年で減価償却した場合、1年目の減価償却費の金額は定額法と定率法で大きく変わります。
- 【定額法】2,000万円×0.25=500万円
- 【定率法】2000万円×0.625=1,250万円
定率法で減価償却する際は定率法償却率・改定償却率・保証率の計算が必要
定率法の減価償却費は、期首残存価額×償却率で計算します。
定率法を計算する際に必要な要素は、こちらの3つです。
- 償却率:法律で決まっている減価償却の償却率
- 改定償却率:償却率を用いて計算した額が償却保証額を下回った場合に、次の年度からの減価償却費の計算で利用される償却率
- 保証率:償却保証額を算出するための割合
上記の数値は法律で決まっており、国税庁が提供しているテーブルに物件の築年数、構造、用途などを当てはめて数値を算出していきます。
この3要素が分かったら、償却保証額と初年度の減価償却費を計算します。
- 償却保証額:取得価額×保証率
- 減価償却費:取得価額×定率法償却率
この時、減価償却費>償却保証額の場合は、その期は減価償却費がそのまま採用されます。
一方、減価償却費<償却保証額の場合は、次の年度から改定取得価額×改定償却率で計算されるようになります。
平成19年4月1日以降の不動産は全て定額法で計算される
取得費を計算する際は、どんな物件も定額法と定率法のどちらかを選べる訳ではありません。
特に平成19年4月1日以降に取得した物件は全て定額法で計算されるようになるので注意しましょう。
それ以前に取得した物件は、特に申請などをおこなわない場合は旧定額法が採用されます。
定率法を利用するためには手続きが必要になるので、こちらも注意が必要です。
不動産売却にかかる譲渡所得税の計算シミュレーション
不動産売却にかかる譲渡所得税の計算は下記の通りです。
- 譲渡所得税=税率×{譲渡価格-(取得費+売却費用) }
計算式をつかって実際の物件売却が成立したときにいくら譲渡所得税がかかるのか見ていきましょう。
成約価格800万円の中古物件のケース
成約価格1,500万円の中古物件Aの場合、下記の計算になります。
| 項目 | 内容 |
|---|
| 取得期間 | 10年 |
|---|
| 成約価格 | 1500万円 |
|---|
| 購入時の価格 | 800万円 |
|---|
| 購入時の費用 | 80万円 |
|---|
| 売却時の費用 | 60万円 |
|---|
この場合、取得期間10年超の軽減税率が適用されたとすると、下記の計算式になります。
約20%×(1500万円-(800万円+80万円-60万円※減価償却費)=約136万円
特別控除を利用すれば税負担をゼロにできます。
成約価格3,000万円の中古物件のケース
例として、以下のような中古物件が成約したとします。
| 項目 | 内容 |
|---|
| 取得期間 | 6年11か月 |
|---|
| 成約価格 | 3000万円 |
|---|
| 購入時の価格 | 2600万円 |
|---|
| 購入時の費用 | 70万円 |
|---|
| 売却時の費用 | 80万円 |
|---|
この時、以下の式で計算をします。
約20%×(3000万円-(2600万円+70万円-60万円※減価償却費)=約62万円
こちらの金額が、物件Aの売却でかかる大まかな納税額となります。
ここから特別控除を使えば、税負担をなしにすることができます。
不動産売却の譲渡所得税を控除する制度
譲渡所得税が発生したとしても、複数ある特別控除を利用することで、課税を減額することができます。
不動産売却で利用できる税金の特別控除まとめ
| 控除が利用できるケース |
所有期間 |
特別控除の内容 |
| 売却益が発生 |
10年超 |
- 買い換え特例
- 3,000万円特別控除
- 軽減税率特例
|
| 売却益が発生 |
5年超10年以下 |
3,000万円特別控除※控除しきれない所得に長期譲渡所得の税率が課される |
| 売却益が発生 | 5年以下 | 3,000万円特別控除※控除しきれない所得に短期譲渡所得の税率が課される |
|---|
ただし、それぞれの特別控除には利用条件が定められており、誰もが利用できる訳ではありません。
税金をシミュレーションする際は、事前に条件を満たしているかどうかのチェックもしていきましょう。
3,000万円特別控除
居住用不動産を売却した時に譲渡所得が発生した場合、そこから3,000万円を特別控除することができます。
マイホーム特例とも呼ばれるこの特別控除を利用すれば、ほとんどの場合、かかる税金を0に抑えることができます。
この3,000万円特別控除を利用する場合は、以下の条件をクリアしている必要があります。
- 住んでいた家を売るか、住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに引き渡すこと
- 親子・親族間の取引ではないこと
- 引き渡し前の2年間で同じ特例を受けていないこと
- 他の特例を受けていないこと
3,000万円特別控除は、相続開始のあった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日以内に売却をすれば相続物件にも適用されます。
この特例を利用するには必ず確定申告をする必要があるので注意しましょう。
取得費加算の特例
取得費加算の特例とは、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年以内に相続物件を売却した場合、取得費に相続税額の一部を含めることができる制度です。
譲渡所得税の大きな減額になりますが、利用する際は以下の条件を満たす必要があります。
- 相続の申告期限の翌日以後3年以内に売却
- 相続税の未納・滞納などがない
- 確定申告が実施されている
加えて、取得費加算の特例をおこなう際はこちらの書類を提出する必要があります。
- 相続税の申告書のコピー
- 相続税の明細書
- 譲渡所得の内訳書
軽減税率の特例
所有期間が10年を超えた場合、譲渡所得税率の計算が以下のようになります。
- 6,000万円以下の部分:年14.21%(所得税: 10.21% 住民税:4%)
- 6,000万円を超える部分:年20.315%(所得税15.315% 住民税:5%)
例えば譲渡所得が8,000万円の場合、軽減税率の特例を使うと以下のようになります。
- 6,000万円×14.21%= 8,526,000円
- 2,000万円×20.315%= 4,063,000円
- 譲渡所得:8,526,000円+4,063,000円=1258万9,000円
この特例は3,000万円特別控除と併用できるのも大きな魅力です。
特定居住用財産の買換え特例
この特例を使うことで、不動産を売却した時に税金を支払うのを、新居を売ったタイミングの支払いに繰り延べることができます。
住み替えにかかる諸費用を抑えることができ、予想以上に収入金額が低かった時の救済策にもなります。
この特例を利用する際は、以下の条件を満たしている必要があります。
- 新居を購入している
- 敷地所有者の所有期間が10年を超えている
- 敷地所有者の居住期間が10年以上である
- 敷地と建物の同時譲渡である
- 敷地と建物の所有者が同居している(別々の場合)
- 譲渡価額が1億円以下である
損益通算及び繰越控除
居住用不動産の譲渡損失特例は、その名の通り不動産を売却して損失が出てしまった場合、つまり譲渡所得がマイナスになった場合に利用できる特例です。
この場合、譲渡所得の損失分を他の所得を使って損益通算することができます。
例えば、給与所得が700万円、譲渡所得の損失が200万円の場合、700万円から200万円を持ってきて相殺します。
そうすると給与所得は500万円になるので、課税される所得が200万円少なくなります
この特例を利用するには、以下の条件を満たしている必要があります。
- 自宅の敷地面積が500㎡以内の部分まで適用
- ※合計所得金額が3000万円以内
- 旧宅売却の年の前年1月1日から旧宅売却の年の翌年12月31日までに新居を取得
- 新居を取得した翌年の12月31日までに入居見込み
- 新居の床面積が50㎡以上
- 新居購入時に返済期間10年以上の住宅ローンを借りている
※譲渡年は、合計所得金額が3000万円超でも損益通算可能ですが、 繰越控除の適用をうける年の合計所得金額は3000万円以下となります。
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
前述の譲渡損失特例は、買換え時以外で利用することはできません。
ただ、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除は買換え資産がなくても実施可能です。
ただ、条件として所有期間5年超である必要があるので注意しましょう。
幅広い取引事例に適用される制度ですが、親族間など近しい間柄の取引は適用外となるケースも少なくないので注意しましょう。
譲渡所得の1000万円特別控除
平成21年~平成22年に取得した土地を売却する場合、譲渡所得から1,000万円を控除することができます。
5,000万円の特別控除の特例
収用とは公共事業のために国が土地を買い取って利用することです。
道路を開通させたり、大規模な施設を建造したりする際に、予想される範囲の中にポツンとある個人の敷地を購入してしまい、まとめて国の土地としてしまうのです。
国の買取は強制力が働くので、その代わりに高額の特別控除が提供されているのです。
この特別控除を利用するためには、以下の条件を満たしている必要があります。
- 売却した日が買取り等の申出があった日から6ヶ月以内
- 売却した人が最初に買い取りの申し出を受けている(6ヶ月以内に相続した場合を除く)
- 固定資産としての土地を売却した場合
また、以下のような税金優遇制度を利用している場合、併用はできないので注意しましょう。
- 収用等の場合の代替資産の特例
- 収用等の場合の交換処分の特例
- 優良住宅地の形成のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
2,000万円の特別控除の特例
区画整理や都市開発といった事業の一環で土地を売却する場合は、2,000万円の特別控除を受けることができます。
この特例を利用するためには、区画面積が最低でも30haである必要があります。
また、以下の特例と併用することができないので注意しましょう。
- 居住用財産・事業用資産の買い替えや交換の特例
- 大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等の場合の譲渡所得の課税の特例
- 認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の譲渡所得の課税の特例
- 平成21年及び平成22年に土地等の先行取得した場合の課税の特例
1,500万円の特別控除の特例
造成とは干拓や埋め立てなどをおこない、土地の用途を大きく変更する作業のことです。
国・自治体や民間企業が造成事業をおこなう一環で土地を買い取る場合、1,500万円が控除されます。
800万円の特別控除の特例
農地を農家へ売却した場合、特別に800万円の控除を受けることができます。
近年は農地の取引が活発化させたい、生産緑地法の期限が切れることで売り出される大量の農地の放棄を避けたいという行政の思惑もあり、1,200万円に控除額が引き上げられるといわれています。
不動産売却の譲渡所得税を節税する方法
不動産売却を行えば、印紙税や登録免許税に加えて、譲渡所得税が売主に課せられます。
税負担の方法として、先ほど紹介した特別控除を利用する手がありますが、利用するには、所定の条件を満たしておく必要があったり、物件種別や状態によっては、利用できないものもあります。
ここからは、特別控除や特例措置以外で譲渡所得税の軽減を図る方法を2つ紹介します。
5年以上所有してから売却する
譲渡所得税は、不動産売却時にかかる税金の中でも、最も負担が大きい税金です。
しかし、先の控除や特例措置をうまく活用すれば節税効果が得られ、税負担そのものの軽減が図れます。
前述で紹介した控除を利用するのも1つの手ですが、売却する時期に応じて、譲渡所得税を軽減することも可能です。
2節「不動産売却で発生する譲渡所得税とは?」で紹介した、所有期間の長さに応じて譲渡所得税が異なる特性を活用すれば、控除同様の節税効果が得られます。
所有する不動産を売却した年の1月1日時点で所有期間が5年以上であれば、「長期譲渡所得税」、5年以下であれば、「短期譲渡所得」とみなされ、課される税率が15%も違います。
節税を試みるなら、控除利用と不動産の所有期間に注目して売却するのがベストです。
空き家を相続したら3年以内に売却する
親族が住んでいた空き家を相続したら、相続した日から数えて3年以内に売却すると、3,000万円の特別控除と同じ節税効果が得られます。
3,000万円の控除が適用されるかどうかは、譲渡所得の節税を行う上で重要な要素です。
特に実家など、物件は取得費用が不透明な場合が多く、取得費用が安く計算されてしまうため、譲渡所得税の計上がしやすいです。
空き家を相続して、住む予定がない場合は、3年以内に売却してしまうのが得策であり、節税効果も3年前後で大きく変わってきます。
不動産売却時に発生する税金に関する質問
ここでは、不動産売却時に発生する税金に関する質問をいくつか紹介します。
Q.不動産の売却を行って発生した税金の納付は種類によって決まっている?
不動産売却を行うとき、印紙税や登録免許税、譲渡所得税など、多方面で発生した税金を税ごとに設けられた期日までに納付しなければなりません。
例えば、印紙税や登録免許税は、売買契約を結ぶときに収めます。
しかし、譲渡所得税(所得税+住民税)や復興特別所得税の納付時期は、翌年の確定申告を行う2月15~3月15日の間で納付し、住民税に関しては、5月末日以降に納付します。
| 税金の種類 |
納付時期 |
| 印紙税・登録登記税 |
売買契約の締結時 |
| 所得税・復興特別所得税 |
翌2月15日~3月15日(確定申告提出期間内に納付) |
| 住民税 |
5月末日以降(納付書が届き次第納付) |
Q.不動産の種類によって発生する税金は異なる?
土地のみの売却や、戸建て住宅・マンションなど、あらゆる物件種別を売却しても、売主に課せられる税金の種類に違いはありません。
課せられる税金の負担軽減が図れる控除や特例の一部に違いがあります。
例えば、土地を売却した後に課せられる譲渡所得では、取得費と諸費用の差し引きに加えて、造成費や測量費も差し引きの大衆に加えられます。
また物件種別ごとに利用できる特例や特別控除があるので、不動産を売却する前に適用できる特例や控除を調べておきましょう。
Q.不動産売却で消費税がかからない方法はある?
不動産会社に仲介売却の依頼を出さず、売主個人の手腕で売買取引を行った場合に限り、消費税がかかりません。
無論、不動産会社に仲介依頼を出せば、仲介手数料に加えて、消費税が加算されます。
また新築物件を個人間で取り扱った場合、売主の立場が法人として見られるため、消費税の課税と住宅ローン手数料への課税がなされます。
所得税がかからないとはいえ、個人間取引を行うときは、資金面の確認と取引時にかかる支出の確認を合わせて行っておきましょう。
不動産売却では税金の種類と特例控除の内容も把握しておこう
不動産売却でかかる税金を減らすことで、手残りが増えてお得になります。
ただ、高値で売却をした上で節税をしないと意味はありません。
不動産売却にかかる多くの税金・費用は、売却価格に比例して高額になります。
同じマンションを1,000万円で売った場合と2,000万円で売った場合では後者のほうが税金は高額になりますが、(売却価額-税金)の手残りが多いのも後者になります。
例えば譲渡所得税率は所有期間が長いほど減率されますが、その年数分だけ建物は劣化していくので、結果的に損をするようになります。
不動産売却では、まず最大限に高く売ることを目指すことで、はじめて節税の効果が見込めるということは理解しておきましょう。
→家を高く売るコツ!相場以上で高額売却を成功させるための5つのポイント
 不動産事業者様へ【無料掲載募集!】
不動産事業者様へ【無料掲載募集!】