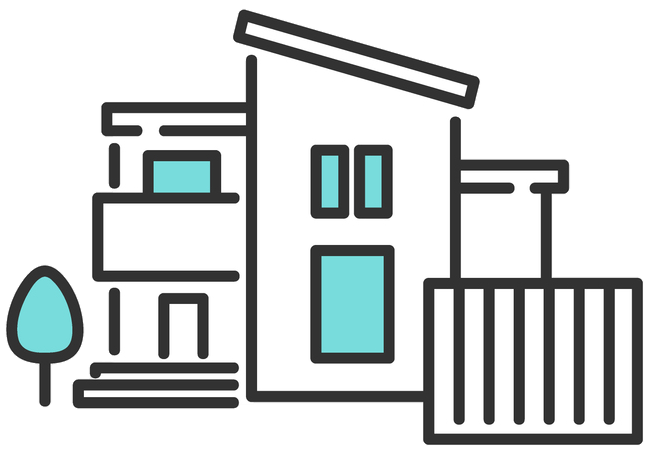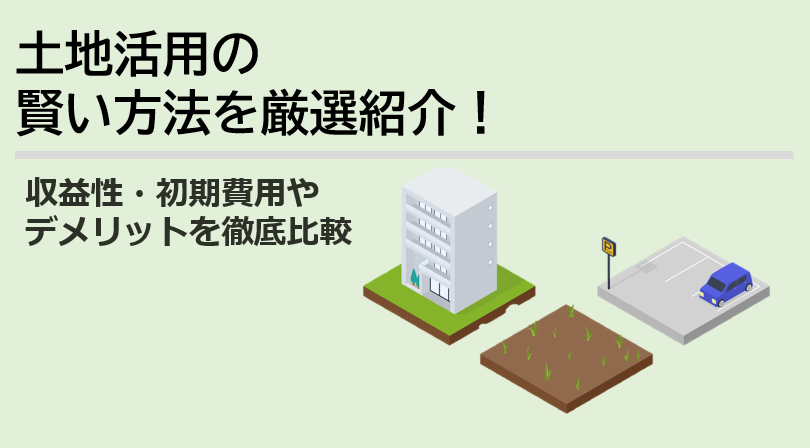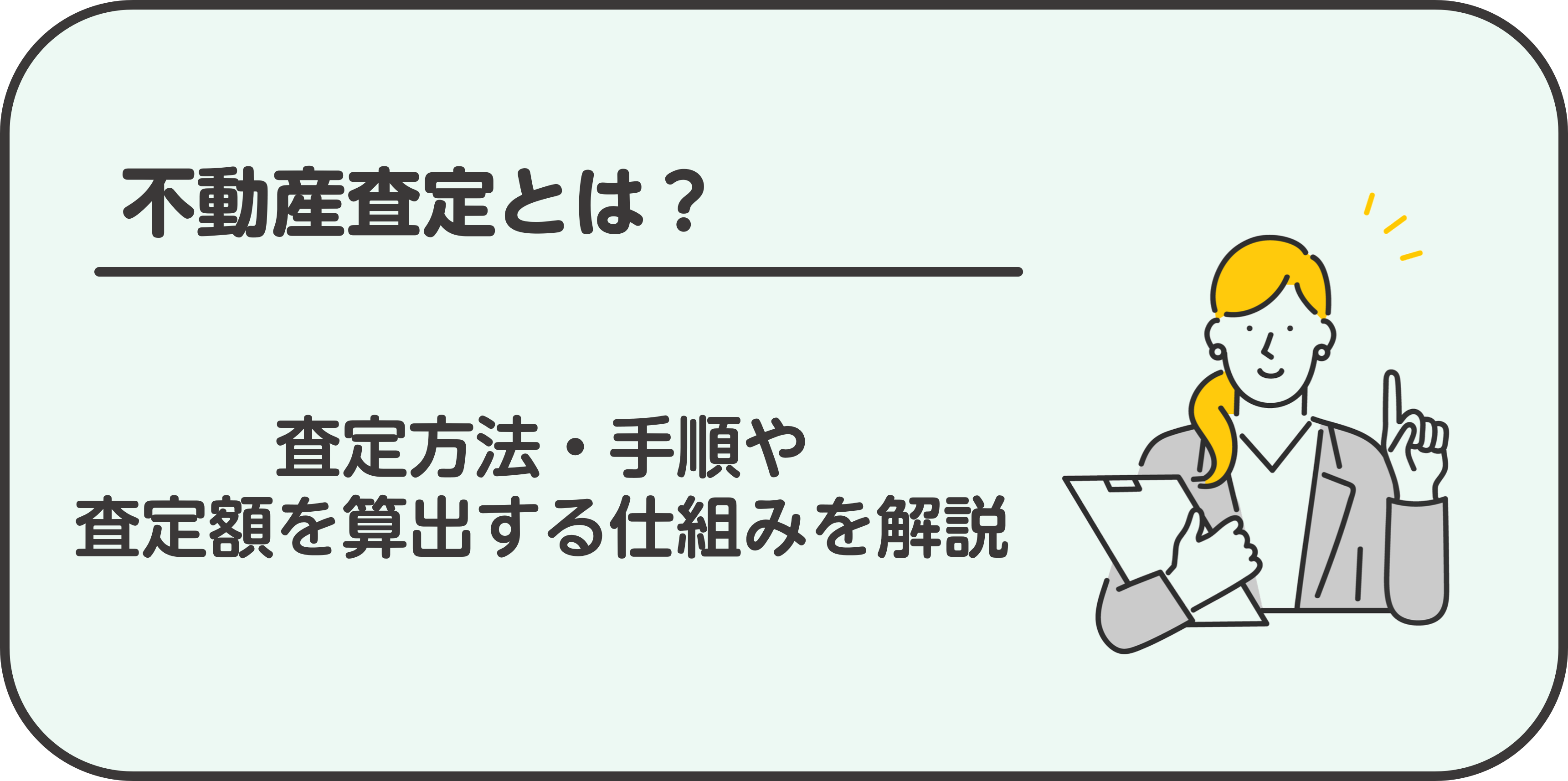不動産事業者様へ【無料掲載募集!】
不動産事業者様へ【無料掲載募集!】
不動産売却した年の固定資産税は誰が支払う?どう精算する?精算の方法・注意点を解説
- 本ページにはPRリンクが含まれます。
- 当サイトでは、アフィリエイトプログラムを利用し各事業者から委託を受け広告収益を得て運営しております。
不動産を所有していると、自動的に固定資産税が課されます。
固定資産税は、毎年1月1日時点で固定資産を有している人に課されますが、それでは、不動産売却の際は大晦日に物件を引き渡さない限り、売却者は損をしてしまいます。
不動産売却時の固定資産税の支払い、精算はどのような考えで行われるのでしょうか。
売り手、買い手の双方が気になっているであろう不動産売却時の疑問を解説していきます。
→不動産売却の方法ガイド|売る前に読むべき鉄則!成功してる人の共通点【2023年最新】
固定資産税の納税義務は売主にある
不動産売却が成功し、1月1日以降に物件を引き渡したとしても、納税者は売り手のままです。
実は、年の途中に不動産売却が完了し、引き渡しが起こった際の固定資産税の取り扱い方法に明確な決まりはありません。
その年の納付書や関連書類は全て売り手のもとに届くようになります。
固定資産税は不動産を所持し続ける限り、毎年納税義務があります。未登記だったり、1月1日以降に立て壊したりしても、自治体が航空写真で把握できる建物の所有者には納税義務があります。
これは年内に売り渡した場合も同じです。
固定資産税の精算は引渡し日を起点にする
不動産売買においては、一般的に売り手と買い手の負担額を日割り計算するという方法が一般的です。
こうして公平に税負担を配分することを、「固定資産の精算」と言います。
ただ、これも法的な取り決めではないので、売り手と買い手の交渉次第では、どちらかが全額負担するということもありえます。
この様に、負担方法は話し合いのもと自由に決めることができますが、もしもの際に責任を負われるのは売り手の方です。
分担をしたら放っておくのではなく、定期的に納税の確認をすると安心です。
固定資産税は原則精算する
不動産売買で発生する費用のうち少額のものは無理に精算をせず、引き続き売り手の負担であることが多いです。
しかし、固定資産税に関しては高額のため、精算をするのが売主にとってのメリットとなります。
もし、買い手が負担に消極的でも、こうした例を出せば負担してもらえやすいですし、ほとんどの業者も精算の交渉を経験しているので、いざという時は任せてしまうのも一つの手です。
1月1日を起算日とすると、どちらかが損をする可能性もあります。
それゆえ、不動産売却が決定した後に、状況に応じて起算日を再決定します。
現在では、1月1日と4月1日のどちらかを選ぶ場合がほとんどです。
ただ、起算日を変更したとしても、1月1日時点で決まった納税義務者に、約半年後、納付書が届けられるので、契約内容や時期が混乱しやすいです。
また、起算日をいつにするかで、売り手と買い手の負担の比重は大きく変わります。
お互いが納得できる決定ができるようにしましょう。
起算日によって精算額が変わる
起算日が1月の場合、1月1日から引き渡し日分は買い手が、引き渡し日から大晦日までの分は売り手が負担するようになります。
一方、起算日が4月の場合、引渡日末までの分は売り手が、それ以降の分は買い手が負担します。
決算日を何月にするか、引渡日をいつにするかによって、負担額は最大で6,7万円も変化します。
これほど負担に差が出るということを知っている人は、あまり多くないです。
とはいえ、相手の無知を利用して勝手に決めてしまっても、後々大きな問題に繋がってしまいます。
無用なトラブルを防ぐ為にも、早めに業者と相談しておいた方が良いでしょう。
関東は1月1日・関西は4月1日が起算日
固定資産税の台帳の更新は1月1日と国が定めています。
ただ、起算日に関しては、関東が1月1日、関西が4月1日となっています。
違う地域の不動産を売却したり、転居者と契約したりする場合は注意しましょう。
固定資産税の計算方法
固定資産税は、土地・建物などの不動産(固定資産)の所有者に課される税金で、地方税に分類されます。
固定資産税は、自治体が地価や再建築価格をもとに算出する固定資産税評価額から計算されます。
固定資産税評価額は、土地か建物かによって考え方が変わります。
- 土地:国の公示地価の約70%
- 建物:再建築価格の約50~70%
固定資産税は、地価の高いエリアになるほど課税額も高くなります。
固定資産税の税率
固定資産税は、評価額(課税標準額)に対して標準税率をかけて算出します。
標準税率は年1.4%が一般的な数字です。
ただ、税率は自治体によって変わることがあるので、注意が必要です。
また、土地と家屋はそれぞれ固定資産税の減額措置が用意されているので、ケースによって課税額が変化する可能性もあります。
固定資産税以外に精算可能な費用
固定資産税以外にも、今まで期限を設定して支払っていた様々な費用を精算する必要があります。
例えば、以下のような費用があります。
- 分譲マンションの家賃
- 水道光熱費
- マンション管理費
- 駐車場代...
費用を精算したいのなら、今かかっている細かい費用を把握した上で事前に引き渡し日を起点に計算しておきましょう。
ただ実際は、年の途中で売買された物件の費用をどう処理するかの明確な法規定はありません。
例えば固定資産税は「1月1日時点の所有者に納税義務がある」と法律に書いてあるので、字義通り見れば精算などできないはずです。
費用の精算はあくまで慣例で認められたイレギュラーなもので、引き渡した年・月締めの費用は売主が支払うのがセオリーです。
それでも精算したいなら、売主のほうから不動産会社に依頼・相談をするようにしましょう。
不動産の固定資産税を精算する際の注意点
固定資産税を精算するときに知っておきたい注意点が、以下の2つです。
- 精算は売買者間の合意でおこなわれる
- 精算は”公式”の手続きではない
ここから、より詳しく説明していきます。
精算は売買者間の合意でおこなわれる
費用の精算は、あくまで2人の合意でおこなわれる手続きです。
買主に拒否されれば自分で全額支払うしかないので、最初から精算できると思わないほうが良いです。
精算手続き自体に費用はかかりませんが、費用の計算時には精算できた場合とできなかった場合の2通りをシミュレーションしておきましょう。
精算は”公式”の手続きではない
税金・費用の精算は価格の値上げ・値下げなどと同じで、ある意味”口約束”によっておこなわれる手続きです。
税務局などもどう精算したか認知しませんし、あくまで売買者・業者の3者間のみが知る手続きとなります。
そのため、もし引き渡し後に支払いトラブルが起きても、話し合いの証拠がなければ相手の言い分をのまざるを得ません。
もし支払われなかった場合のペナルティなども含めてしっかり話し合っておき、それを売買契約書に詳細に書き留めておくのがおすすめです。
→不動産売却の必要書類と取得方法をタイミング別に徹底解説買主との精算トラブルを避けるポイント
固定資産税の精算は金額が大きいので、注意して実施しないとトラブルが発生する可能性が高いです。
ここからは、固定資産税の精算でトラブルにならないためのポイントを紹介していきます。
精算の有無を契約書に明記する
固定資産税の精算は義務ではないため、そもそも不動産取引の中で精算するかどうかを決める必要があります。
固定資産税の納付は1月1日時点の所有者が対象になるので、精算がない場合は買主が得をして売主が損をします。
売主の立場なら、まず固定資産税を精算することをはっきり確定させて、契約書に盛り込む必要があります。
起算日・精算額をはっきりさせる
固定資産税を精算する際に、売主・買主間で話し合った起算日・精算額に認識のズレがあると、後々トラブルが発生します。
話し合って合意をしたら、その内容を必ず契約書へ明記しましょう。
口約束ではなく、契約書に明記をすることでトラブルにも対応しやすくなります。
精算金には消費税が課される
固定資産税の課税自体には消費税が課されませんが、清算金は消費税の課税対象となります。
金額次第では結構な負担になるので、事前に消費税課税分の金額も把握しておくようにしましょう。
固定資産税は経費に入らない
固定資産税は不動産売却で発生した経費として計上できないので、注意が必要です。
不動産売却で利益(売却益)が出ると、譲渡所得税が発生します。
- 譲渡所得税=※課税譲渡所得×税率
- ※課税譲渡所得=譲渡価額(売却代金) -取得費(購入費用)-譲渡費用(売却費用)
不動産売却でかかった経費を譲渡費用(売却費用)に計上することで、課税対象額を下げることが出来ます。
ただし、固定資産税は経費とはみなされないので、税金とは別で支払いが必要です。
買主が支払いを拒否するケースもある
固定資産税の精算は慣習で買主も支払うケースが多いですが、買主にとってはデメリットなので拒否されるケースもあります。
この場合、売主と買主で清算金の支払いについて揉め事が起これば、最終的に契約が破談になってしまう可能性も出てきます。
こうなってしまうと売主側のデメリットのほうが大きくなってしまうので、注意が必要です。
固定資産税の精算でトラブルが起こりそうな場合は、仲介業者にまず相談をして、対応を代わってもらいましょう。
不動産売却時の固定資産税のポイントをおさらい
不動産売却時の固定資産税は誰がどう支払う?
不動産売却時の固定資産税の納税義務は、原則として売主にあります。
この税は1月1日時点での不動産所有者に対して課せられ、年の途中で売却が完了しても売主が納税義務者となります。
ただし、固定資産税の精算は通常、売主と買主間で日割り計算によって公平に分担されるのが一般的です。
精算の方法は交渉により決定され、1月1日または4月1日を起算日として選択するケースが多いですが、契約内容や時期によって負担額が大きく変わるため、双方が納得できるように話し合いましょう。
固定資産税の計算方法は?
固定資産税は、土地や建物などの不動産に対して課される地方税です。
計算式は「固定資産税評価額×標準税率(年1.4%)」で、評価額は土地は公示地価の約70%、建物は再建築価格の約50~70%で算出されます。
ただし、税率は自治体によって異なることがあります。
不動産売却時の固定資産税の精算は注意が必要
仲介業者の役割は、物件の引き渡しまでとなります。
それゆえ、固定資産税の存在を業者は見落としがちです。
売り手・買い手間のみで取り決めをすることも可能ですが、第三者がいてくれた方がトラブルに発展しにくいです。
不動産業者の立会いのもと、日割り計算についてだけでなく、起算日をいつにするかまで、しっかりと話し合っておくことが大切です。
また、税負担の配分は、あまり早く決めてしまうと売買契約の結果に影響してしまうので、お薦めはできません。
なるべく、契約が決まった後に話しを切り出すと良いでしょう。