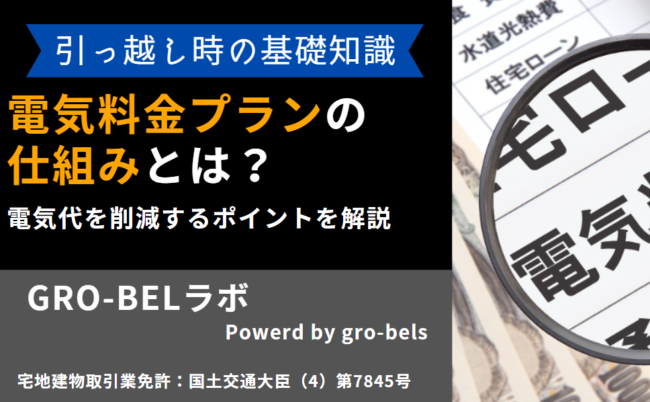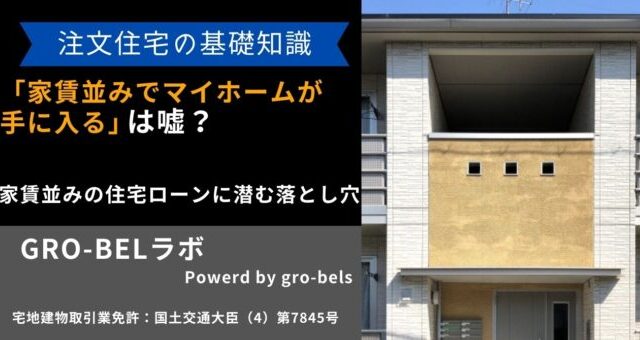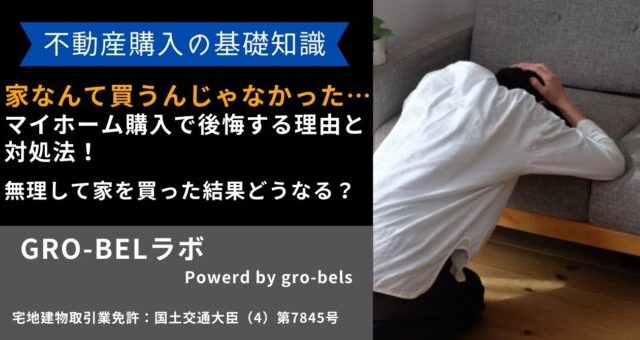日常生活を送るうえで、毎月支払っている電気料金は、今住んでいる住居で暮らす際に契約した電気プランの内容に応じて、毎月収める料金が決定します。
当然ですが、電気料金の料金プランは、電力会社・新電力会社に応じてプラン内容が異なります。
プランの中には、ガスやインターネット回線など、電気以外のサービスが付いてくるものも存在し、そちらを契約すると、セット割が適用されて、今以上に利用金が安くなることもあります。
今回は、電気料金の契約プランの徳見や自分生活に合った料金プランの見直し方を紹介します。
| サービス料金 | 問い合わせ |
|---|---|
| 無料 | LINE |
| 解約・導入手続き | 土日祝対応 |
| コンシェルジュ対応 | 可能 |
-
電気・ガス・水道・ネット回線手続きが電話1本で完了
-
契約料金の見直し・相談から些細な相談まで対応可能!
-
専門コンシェルジュが不明点は徹底的にサポート!
- 電話申込時の混雑を待たなくて済む!
電気料金プランの仕組み
電気料金は、私たちの日常生活に密接に関わるもので、その料金体系を理解することは重要です。
ここでは電気料金プランの主要な構成要素について、基本料金、電力量料金、燃料費調整額、再エネ賦課金の4つの観点から解説します。
基本料金
基本料金は、電力供給に必要な固定費をカバーするために設定されています。
この料金は、使用する電力の量に関係なく毎月一定額が請求されます。
- 契約している電力会社
- 選択したプランの内容
- 契約した電気のA(アンペア)数
基本料金の額は、上記3つの要素を掛け合わせることで金額が決定し、詳細な金額は会社によって異なります。
また基本料金は、会社が持つ以下の諸経費をカバーする目的で徴収しています。
- 発電設備の維持管理費
- 人件費
- 機材の購入や維持費
- その他経営に必要な諸経費のカバー
電気を全く使用しなかった場合でも、この基本料金は支払う必要があります。
電力量料金
電力量料金は、実際に消費した電力量に基づいて計算される変動費です。
この料金は使用した電力量に応じて変化し、電力量料金単価と使用電力量を乗算して算出されます。
多くの電力会社では、消費電力量に応じて料金単価が異なる階段式の料金体系を採用しており、使用電力量が増えるほど単価が高くなる傾向にあります。
電力量料金の計算式には、燃料費調整額が加算または減算されます。
燃料費調整額
燃料費調整額は、発電に使用する燃料の価格変動を電気料金に反映させるための調整金です。
この金額は、「燃料費調整単価 × 使用電力量」の式で計算され、電力量料金に加算または減算されます。
燃料費調整単価は、過去3カ月間の燃料価格の平均に基づいて設定され、2カ月後の電気料金に反映される仕組みです。
燃料価格の急激な変動が電力会社の経営に与える影響を緩和するためにこの制度が導入されています。
再エネ賦課金
再エネ賦課金は、再生可能エネルギー源からの電力を支援するために設けられた料金です。
この賦課金は、太陽光や風力などの再生可能エネルギーを利用した発電によって生産された電力の買取りコストを消費者に配分する目的で設定されています。
計算式は上記の通りで、この単価は経済産業大臣によって年度ごとに決定され、全国で一律です。
この制度により、再生可能エネルギーの普及と発展が促進されています。
電気料金の「電気料金制」の種類
電気料金制度は、消費者の電力使用状況やニーズに応じて様々なプランが提供されています。
この記事では、電気料金の計算方法として一般的に用いられる「基本料金制」、「定額料金制」、そして「従量料金制」の三つの主要な制度について、それぞれの特徴と適用状況について解説します。
基本料金制
基本料金制は、毎月一定の基本料金と、実際に使用した電力量に応じた料金が加算される二部料金制です。
この制度は主に事業所や工場など、一定量以上の電力を定期的に使用する場所で採用されています。
また基本料金は、電力供給のための設備維持や運営コストをカバーするために設定されており、使用電力量に応じた料金は、消費者の電力使用量に応じて変動します。
定額料金制
定額料金制は、使用する電力量にかかわらず毎月一定の料金を支払う制度です。
このプランは、電力使用量が多い消費者や電力使用が一定している事業所に適しています。
定額制のメリットは、電力使用量が多くなっても料金が変わらないため、予算計画が立てやすいことです。
しかし、少ない電力しか使用しない場合は、他の料金制より高くなる可能性があります。
従量料金制
従量料金制は、使用した電力量に応じて料金が計算される制度です。
この制度は、特に一般家庭で広く導入されています。
料金は使用した電力量の区間ごとに設定された単価に基づいて計算され、15kWhを最低使用量とし、それを超えると追加料金が発生します。
従量料金制のメリットは、使用電力量に応じて料金が調整されるため、節電効果が直接料金に反映されることです。
電気料金『従量電灯プラン』の仕組み
電気料金の中で広く利用されている従量電灯プランは、家庭や事業所での電気の使用状況に応じて最適な料金体系を提供します。
是術したように、従量料金制を採用した「従量電灯プラン」は、電力使用量に応じて料金が計算されることが特徴で、消費者のニーズに合わせた柔軟な料金設定が可能です。
従量電灯プランには、基本料金制と最低料金制の2つの異なる料金体系があり、これらは電力会社や契約内容によって異なります。
またここからは、電気料金『従量電灯プラン』の特徴に触れながら、一般的な料金プランとの違いについて解説します。
電気料金プラン『従量電灯A・B・Cなど』の違い
従量電灯プランは、契約する電力の量によって、従量電灯A、B、Cなどの異なるカテゴリーに分けられています。
- 従量電灯プランA:集合住宅の共用部の照明
- 従量電灯プランB:一般家庭向け料金プラン
- 従量電灯プランC:法人向け料金プラン
これらのプランは契約容量が大きくなるほど高く設定されており、それぞれのニーズに合わせた料金プランが用意されています。
しかし、電力会社によっては従量電灯A・Bのように2種類だけ提供している場合もあります。
従量電灯プラン内にある『基本料金制』と『最低料金制』の違い
従量電灯プランでは、基本料金制と最低料金制の2つの料金体系が存在します。
| 料金プラン | 概要 |
|---|---|
| 基本料金制 | 契約する電力の量(アンペアなど)によって基本料金が変わるシステムで、消費者が選択した契約容量に応じて料金が設定されているプラン。 |
| 最低料金制 | 契約容量の設定がない代わりに、1契約あたりの最低料金が設定されているプラン。 |
これにより、電力使用量が少ない場合でも一定の料金が保証されます。
各電力会社はこれらの制度を採用しており、消費者は自分の電力使用状況に最も適したプランを選択することができます。
電気料金が高騰している原因
近年、電気料金の高騰は多くの消費者に影響を与えています。
この高騰の背景にはいくつかの重要な要因があります。
- 電力の供給不足
- 燃料費調整額の高騰
- 円安による燃料輸入費の高騰
以下では、これらの要因について詳しく解説します。
電力の供給不足
日本における電力供給不足は、特に東日本大震災後の原子力発電の停止が大きな要因です。
多くの原子力発電所の停止により、日本の電力供給量に影響が出ています。
また、火力発電所の老朽化による休廃止も進んでおり、火力発電が占める電力供給量の縮小が見られます。
このような電力供給の不足は、電気料金の高騰に直結しています。
燃料費調整額の高騰
日本の電源構成の大部分を占める火力発電は、主に化石燃料に依存しています。
国際情勢の変動や円安により、これら燃料の価格が上昇すると、発電コストが増大し、結果として燃料費調整額が高騰します。
燃料費調整額は、直接電気料金に反映されるため、その上昇は消費者の負担増となります。
円安による燃料輸入費の高騰
円安が進むと、外国からの燃料輸入費が増加します。
特に2022年以降、円安が進行し、火力発電に必要な燃料の輸入コストが上昇しています。
この状況は、電気料金に直接的な影響を与えており、消費者の電気料金の負担増加に繋がっています。
円安が一時的に落ち着いたとしても、その影響は電気料金に長期間影響を及ぼすことがあります。
電気料金を見直す方法
電気料金を節約するには、契約内容の見直しや電力会社の変更を検討することが効果的です。
- 契約アンペア数の見直し
- 電気料金プランの選択
- 新しい電力会社への乗り換え
ここからは、上記3つの方法について解説します。
契約しているアンペア数を見直す
多くの家庭では、基本料金がアンペア制で設定されています。
契約しているアンペア数が多いほど基本料金も高くなるため、現在の使用状況に合わない高いアンペア数で契約している場合、アンペア数を下げることで基本料金を削減できます。
ブレーカーが落ちることがほとんどない場合や、使用電力が少ない家庭は特に見直しを検討する価値があります。
また、一部の電力会社では基本料金が0円のプランも提供されています。
契約している電気料金プランを見直す
多くの家庭では標準的な従量電灯プランが適用されていますが、このプランは電力使用量に応じて料金が上がるため、使用状況によっては最適でない場合があります。
電力会社ごとにさまざまな料金プランが提供されています。
- 時間帯別割引プラン
- ガスや通信サービスとのセット割引
生活スタイルに合わせて最適なプランを選択することで節約につながります。
定期的にプランを見直し、より適したものに変更することが節約の鍵です。
新電力会社に乗り換える
電力小売自由化により、消費者は自由に電力会社を選べるようになりました。
現在利用している電力会社よりも安いプランを提供する新電力会社に乗り換えることで、電気料金の削減が可能です。
乗り換えを検討する際は、料金プランだけでなく提供されるサービスの内容や顧客サポートも比較することが重要です。
電力会社を変更しても電気の品質に影響はなく、これまで通り安定した電力供給を受けることができます。
電気料金の仕組みを理解すればプランの見直し・料金削減につながる
電気料金削減の鍵は、その仕組みを理解することにあります。
電気料金は、基本料金、電力量料金、燃料費調整額、再エネ賦課金など複数の要素から構成されています。
基本料金は電力供給の固定費用をカバーするもので、アンペア数やプランによって変わります。
電力量料金は使用した電力量に基づいており、電力使用量が増えると単価が高くなる傾向があります。
燃料費調整額は燃料価格の変動を反映するもので、国際情勢により変動します。
再エネ賦課金は再生可能エネルギーの推進に関連しています。
以上のように、電気料金の構成要素を理解し、それらがどのように料金に影響を及ぼすかを知ることは、効果的な料金削減戦略を立てるうえで非常に重要です。
さらに、自分の生活スタイルや電力需要に合わせたプラン選択や契約内容の見直しにより、無駄な電気代の支払いを避け、経済的な電力利用が可能になります。
![GRO-BELラボ[株式会社グローベルス]](http://gro-bels.co.jp/labo/wp-content/uploads/2024/08/ラボ ロゴ-02-1.jpg)