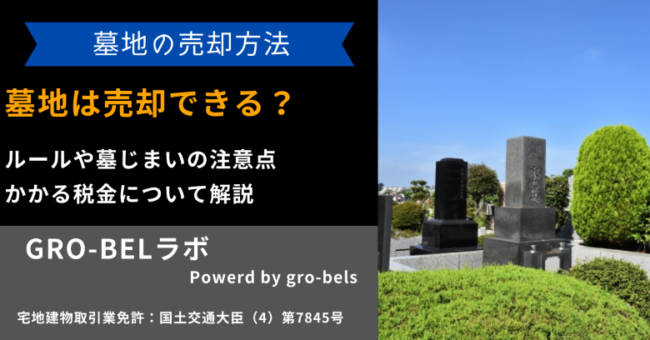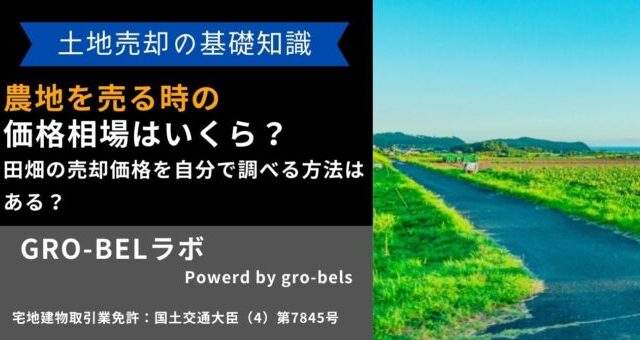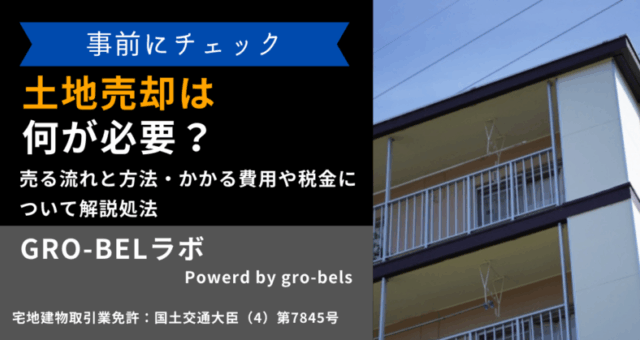近年、実家を離れた、仕事が忙しいという理由で先祖のお墓の管理をする時間や余裕がとれず、荒れた墓地が増えているということが大きな問題になっております。
そのような事情のためにお墓の管理ができないのであれば、お墓およびその土地を売却してしまうのが理想です。
ただ、実際にお墓とその土地を売却するときはどのような手続きがおこなわれるのでしょうか。
今回はお墓や、その土地を売却する方法や注意点を解説します。
墓地の売却は可能だが難しい理由
理由1】墓地は不動産そのものではなく永代使用権を取引する
墓地の売却が難しい最大の理由は、多くの墓地が所有権ではなく永代使用権という形で利用されているためです。
一般的な不動産取引では、土地や建物の所有権を売買しますが、墓地の場合はあくまで“その場所をお墓として使用する権利”を得ているだけに過ぎません。
これは不動産登記される土地とは異なり、売買の対象として明確に扱いにくい権利形態です。
また、実際の所有者は霊園や寺院などの管理者であるため、たとえ永代使用権を得ていても勝手に第三者に譲渡・売却することは原則できません。
例えば、ビジネス上とても価値のあるエリアの土地が墓地として利用されているため購入できない、、という事例も昔から少なくありません。
理由2】譲渡禁止特約が契約に含まれていることがある
墓地の契約書には、しばしば譲渡禁止特約が設けられています。
これは、契約当事者がその権利を第三者に譲渡することを制限する条項であり、永代使用権の移転に大きな制約を与えます。
契約上の地位の移転
民法 第五百三十九条の二 契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において、その契約の相手方がその譲渡を承諾したときは、契約上の地位は、その第三者に移転する。
引用:「民法」e-gov法令検索より
実際には、民法第539条の2により、契約上の地位の譲渡は「契約相手方の承諾がある場合に限り有効」と定められています。
そのため、譲渡禁止特約が存在する場合、霊園や寺院などの管理者が承諾しない限り、第三者への売却は成立しません。
ただし、この特約は法的には“当事者間の合意”に過ぎず、事情によっては話し合いの上で譲渡が認められる可能性もゼロではありません。
しかし、承諾が得られるケースは少数であり、実際に取引が成立するケースは珍しいと考えておく必要があります。
理由3】宗派の教義などを満たさない使用は認められない
墓地の多くは、宗教法人や寺院が所有・管理しており、利用者には特定の宗派の教義や儀式への同意が求められます。
このため、永代使用権は契約上、宗派の規則に則って利用されることが前提となっており、第三者への譲渡・転売は現実的に難しいとされています。
実際、宗派に反する供養や無断での名義変更が行われた場合、使用規則違反として永代使用権が取り消される可能性もあります。
つまり、売却を前提に考えた場合でも「買い手が限定的にならざるを得ない」「契約条件によってはそもそも取引が成立しない」といった制度上のハードルが高いため、墓地は他の不動産と異なり売却が極めて困難な資産と言えます。
墓地を利用者が売却できるケース(自用墓地・個人墓地)
墓地の中には、極めて限られたケースですが所有権付きの墓地も存在します。
これは、不動産登記上も土地の所有権が個人に帰属しているタイプの墓地であり、通常の土地と同じように売買や相続が可能です。
たとえば、地方の古い墓地や、個人所有の私有地に設置された墓地(自用墓地・個人墓地)などが該当します。
ただし、所有権付きであっても、墓地としての利用にあたっては条例や宗教法人法などの規制がかかることがあるほか、霊園管理者との契約条件により制限が課されている場合もあります。
単に所有権があるからといって自由に売却できるわけではない点に注意が必要です。
不動産登記されている場合は通常の土地売却に近い
墓地が登記簿上も宅地や墓地用地として所有者名義で登録されている場合、その土地は法律上の不動産として扱われます。
そのため、売却には以下のような一般的な不動産手続きを経ることになります。
- 所有権の登記情報の確認
- 測量・境界確認
- 買主との売買契約書締結
- 法務局への所有権移転登記
加えて、売却益が発生すれば譲渡所得税などの税金も通常通り発生します。
土地利用の自由度が高い反面、墓地としての用途制限や周囲との調整が必要となるケースもあるため、慎重な対応が求められます。
霊園管理者の同意が必要なことがある
仮に墓地の所有権を保有していたとしても、周辺一帯が宗教法人や自治体などによって一括管理されている墓地であれば、売却に際して管理者の同意が必要となる場合があります。
特に、共有設備(参道・水道・駐車場など)を伴う大規模霊園では、土地の一部だけを独立して処分することが実務上困難なケースもあります。
また、買主が墓地としての再利用を希望する場合、宗派や霊園規約との整合性も問われます。
このため、所有権がある場合でも、売却の可能性を判断するには次の点を事前に確認することが重要です。
- 登記簿上の名義と用途区分
- 管理規約や使用細則
- 管理者(宗教法人・自治体)との契約内容
個人での判断が難しい場合には、不動産会社や司法書士・行政書士などの専門家に相談しましょう。
お墓の売却時に重要な土地の永代使用権とは?
永代使用権の基本的な仕組み
お墓を購入する際、多くの人が「墓地の土地を買った」と思いがちですが、実際には土地そのものを取得したわけではありません。
墓地を購入する際には墓地を永代に亘って使用できますよという永代使用権を購入した上で敷地内に墓石を建立し、更に毎年年間管理費を払うことになり、実質的には借地の上に購入した自分の持ち物である墓石が乗っているという形になりますので、使用者は墓地の所有権を持っているのですが、厳密には借地権と墓石を所有することになります。
引用:NPO法人やすらか庵 公式HPより
購入しているのは永代使用権と呼ばれる、墓地の区画をお墓として使用し続ける権利です。
この権利に基づいて墓石を設置し、霊園や寺院などの管理者と契約を結び、さらに毎年の管理料を支払いながら利用するのが一般的な形態です。
つまり、墓石の所有権は個人にあるものの、土地についてはあくまで“使用させてもらっている”状態にとどまります。
永代使用権は法的には「地上権」「貸借権」「使用貸借権」に類似した性質を持つ、慣習的な権利とされています。
このため、法的保護の範囲も限定的であり、不動産取引のように第三者へ自由に譲渡・売却できる類の権利ではありません。また、不動産登記もなされないため、法的な対抗力にも限界があります。
その本質が「使用の許可」に過ぎない以上、売却や譲渡を行うには、管理者(霊園・寺院)側の承諾が不可欠となるのが実態です。
管理者(霊園・寺院)に無断で譲渡・売却できない
永代使用権の契約には、ほぼ必ず第三者への譲渡禁止や承諾なき使用名義変更の禁止といった条項が含まれています。したがって、使用者が勝手に権利を売却・譲渡することはできません。
たとえ親族間であっても、名義変更には所定の手続きが必要であり、許可を得ない限り永代使用権の承継が認められないケースもあります。
購入時点で契約内容をよく確認し、売却・譲渡が原則できないことを理解しておく必要があります。
使用状況によっては永代使用権が取り消されることもある
永代使用権といっても、永遠に保障されるものではありません。契約に基づくものである以上、一定の条件を満たさなければ解除・取り消しの対象となることがあります。
たとえば、以下のようなケースでは永代使用権の消滅が生じることがあります。
- 名義人が死亡し、承継者の手続きが行われていない
- 無断で第三者に譲渡した場合
- 墓地以外の用途に利用された場合
- 長期間にわたって管理費が未納である場合
- 名義人が改宗し、宗派に沿った利用ができなくなった場合
墓じまいをしたら永代使用権の処分・売却は可能?
墓じまいとは、遺骨を他の場所に移す改葬や、墓石の撤去、永代使用権の契約終了などを含む、墓地を閉じることを指す俗語です。
最近では少子高齢化、核家族化などもあり、墓じまいをおこなう例が増えています。
墓じまいをしても永代使用権は原則として売却できない
永代使用権とは、霊園や寺院が所有する墓地をお墓として使用することを許可された権利であり、土地そのものの所有権ではありません。
このため、墓じまいを行って使用を終了したとしても、永代使用権を第三者に売却・譲渡することは原則として認められていません。
墓じまいはあくまで墓地の利用を終了し、返還する手続きであり、資産としての処分・売却が可能になる訳ではありません。
私有墓地を売却する場合は墓じまいが前提となる
一方で、墓地を私有している場合は売却が可能ですが、現実的に考えて今の所有者の一族の墓石や遺骨がある状態のまま売買が成立することはありません。
これは精神的な要因もありますが、登記上の地目が墓地になっているため、住宅用地として利用できないという現実的な問題もあります。
そのため、墓じまいをおこない改葬・更地化をおこなった上で、地目を変更して売却するというフローが現実的に必要となります。
墓じまいの費用は最大で約100万円になる
墓じまいにかかる費用は、以下のようなものがあります。
- 閉眼供養
- 離檀料
- 墓石解体費用
- 墓石撤去費用
- 整地作業の費用
- 遺骨の運搬費
これらの費用を合計すると、50~100万円にものぼってしまいます。
墓地を売ったからといって、これらの費用を必ずしも回収できるわけではないので注意しましょう。
墓地売却にかかる税金・費用・手数料
墓じまいをした土地を売却した場合は、通常の不動産と同様に譲渡所得税や印紙税などの税金が発生します。
| 土地売却で発生する税金 | 納付方法 |
|---|---|
| 印紙税 | 売買契約締結時に収入印紙を貼り付けて納付 |
| 登録免許税 | 登記時に納付 |
| 譲渡所得税(所得税・住民税・復興特別所得税) | 確定申告で納付(引き渡しの翌年2月16日から3月15日まで) |
| 消費税 | 仲介手数料、司法書士報酬、銀行手数料などを支払い時に発生 |
| 法人税・法人住民税・法人事業税 | 事業年度終了日の2ヵ月前以内に納付 |
墓地売却で起こりやすいトラブルと対処法
トラブル1】使用目的や契約内容のズレ
墓地の売却では、買主との間で使用目的に関する認識のズレからトラブルが生じるケースがあります。
たとえば、買主が「墓地以外の用途で使える」と誤解して購入しようとした場合、用途制限により取引が成立しない、または無効になる可能性があります。
また、永代使用権の場合は土地の所有権がないため、「売却できると信じて購入したのに、名義変更ができなかった」といったトラブルも報告されています。
トラブル2】霊園管理者・宗教法人の同意が得られない
墓地を管理する霊園や宗教法人の同意がなければ、譲渡・売却ができないケースが多くあります。
たとえ所有権付き墓地であっても、霊園全体の運営方針や規約に反する場合は、売却に制限がかけられる可能性があります。
契約書や霊園規則を事前に確認し、早い段階で管理者との協議を行うことが重要です。
トラブル3】名義人が不明・相続未登記のままで売却できない
墓地の名義人が亡くなっている場合、そのままでは売却手続きが進められません。
相続登記が行われていないと、売却の権利を証明することができないためです。
このような場合には、まず相続人間で話し合い、必要な手続き(遺産分割協議書の作成、相続登記など)を済ませた上で、名義変更を行う必要があります。
名義人が不明確な状態では、売却契約そのものが無効になる恐れもあるため、注意が必要です。
トラブル4】境界・面積・地目が曖昧
墓地が所有権付きの土地である場合でも、登記情報と現況が一致していないと、買主との間でトラブルが起こることがあります。特に以下のようなケースは注意が必要です。
- 登記簿上の地目が「墓地」ではなく「山林」や「原野」になっている
- 隣接地との境界が不明確である
- 測量が古く、実測面積と大きく異なる
このような状況では、売買価格の交渉が難航したり、契約自体が取りやめになる可能性があります。
そのため、売却前に測量や法務局での情報確認を行う必要があります。
墓地の売却件数は増加の傾向
 墓じまい件数の推移 引用:朝日新聞
墓じまい件数の推移 引用:朝日新聞自分の家の墓地の手入れが困難になってしまった方は年々増え続けている傾向にあります。
また、お墓の管理者がいなくなってしまった無縁墓も増え続けており、大きな問題になっております。
そのような中で不要になったお墓の土地を売却してしまいたいと考えている方も多くいますが、そこには永代使用権と所有権が契約の際に分離されているため、墓地を売るためには所有権を保有している必要があります。
墓地を売りたいと考えている方は是非、墓地の所有権の有無に関して確認してみるとよいでしょう。
墓地売却は難しい上に負担も大きいので要注意
多くの場合、墓地の売却は「墓じまい」が前提となります。遺骨を移す改葬の手続き、墓石の撤去、更地化、離檀料の支払いなど、経済的・手続き的な負担は小さくありません。
また、墓じまい後に土地の用途が変更されると、固定資産税や譲渡所得税の課税対象になる可能性もあるため、税務上の影響についても理解が必要です。
加えて、現実的に考えて墓じまいをした墓地跡には買い手がつきやすいということはないので、市場を考えても難しい売却になる可能性は高いでしょう。
売却という選択肢だけに固執せず、改葬・永代供養なども含めて、自身や家族の価値観、将来的な管理負担を踏まえて、最適な方法を選ぶことが大切です。
![GRO-BELラボ[株式会社グローベルス]](http://gro-bels.co.jp/labo/wp-content/uploads/2024/08/ラボ ロゴ-02-1.jpg)