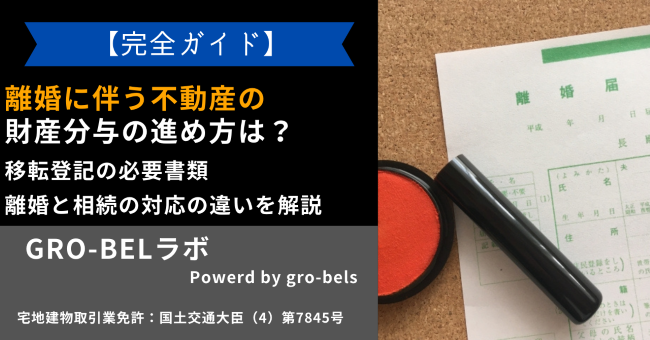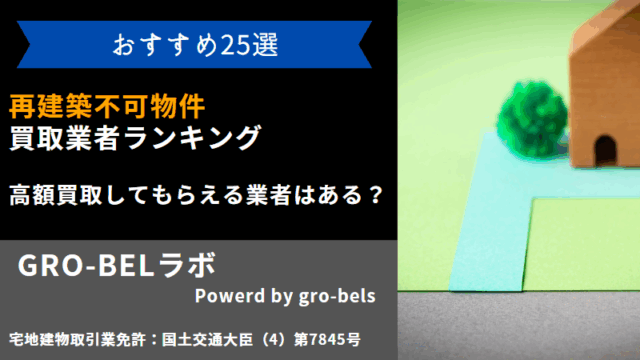| 相談内容 | 回答 |
|---|---|
| 夫婦名義で住宅ローンを組んだ家をどちらかが住み続ける場合、査定をして買い取ったことにして財産分与をする? | 査定額を基準にして「家の時価 − ローン残債=純資産」を算出し、住まない側に金銭で清算(代償分与)する形が一般的です。 |
| 住宅ローンの名義が夫、連帯保証人が妻で、かつ査定額よりローン残債額が多い場合はどうする? | ローン残債>査定額なら「オーバーローン」となり、任意売却が必要になる場合があります。債務整理や自己資金の持ち出しも検討する必要があります。 |
| 夫婦名義で住宅ローンを組んだ家をどちらかが住み続ける場合、出ていく方が清算金を捻出できない時はどうする? | 財産分与の観点では居住希望者が査定額で買い取るのが原則ですが、金額を交渉したり、居住権の期間付き設定をしたりするケースもあります。 |
| 離婚がこじれており、元夫が査定に協力してくれない時はどうする? | 家庭裁判所での調停・審判を通じて、無断拒否が認められない状態にすることができます。 |
| 査定額が不動産会社によってバラバラで判断できない場合はどうする? | 複数の業者の平均値や中央値をとることが多いですが、その上でやや低めの金額設定になる傾向にあります。 |
| 家の売却が遅れて引っ越しなどの見通しも立てられなくなっている場合はどうする? | 短期間のリースバックを検討したり、公的支援の利用を検討するのも一つの手です。 |
離婚や相続で財産分与をするとなった場合、資産価値が最も大きく、財産の多くを占めるのが不動産です。
不動産の財産分与を円滑に進められるかによって結果が大きく左右されると言っても過言ではありませんが、金額が多い分、様々な注意点を知っておかなければいけません。
本記事でお伝えする内容は、以下のとおりです。
- 離婚に伴う財産分与の種類
- 不動産を財産分与する流れ
- 不動産を財産分与する方法
今回は、財産分与を検討している人にも分かりやすく、疑問・質問を解決していきます。
- 離婚時に行う財産分与とは?
- 離婚時に財産分与をしない方法はある?
- 離婚時に財産分与をしない場合の対処法
- 離婚に伴う財産分与の種類
- 離婚に伴う財産分与の対象になるものとならないもの
- 離婚時の財産分与でよくあるトラブル事例
- 離婚時の財産分与のトラブルを防ぐ方法
- 財産分与の前に不動産を査定に出した方が良い理由
- 不動産の財産分与を行うケースは主に2通り
- 不動産の財産分与は換価分割という考え方で行われる
- 不動産を財産分与する流れ
- 離婚のために不動産を財産分与する方法
- ローンあり不動産を財産分与するときの計算方法
- 不動産は売却してから財産分与をした方が良い理由
- 離婚時の財産分与で不動産を売るときの注意点
- 離婚後に夫(妻)が家やマンションに住み続けると住宅ローンはどうなる?
- 条件付きで不動産の財産分与が認められるケース
- 財産分与の請求期限に時効はないが早めにすべき理由
- 財産分与の除斥期間2年を延長する方法
- 不動産の財産分与は子供も入れて計算する?
- 財産分与で相手が財産を隠していた時はどう対処する?
- 不動産の財産分与に税金はかかる?
- 財産分与では不動産をどうするか優先的に考えよう
離婚時に行う財産分与とは?
離婚時の財産分与は、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産を、離婚に際して分け合う手続きです。
このプロセスでは、マンション、一戸建て、土地などの不動産をはじめ、預貯金、自動車、生命保険など、婚姻中に得た財産が全て対象になります。
たとえこれらの財産がどちらか一方の名義であっても、実質的には夫婦の共有財産とみなされます。
法律上の基本的な原則は、「夫婦が半分ずつ」財産を分け合うことです。
これは、夫婦がそれぞれ婚姻中に財産形成に同等の貢献をしたと見なされるためです。
例えば、専業主婦や収入が夫より低い妻であっても、財産分与において不利に扱われることは原則としてありません。
これは、夫が仕事に専念できたのは妻の支えがあったためと評価されることが多いです。
離婚時に財産分与をしない方法はある?
離婚するときに財産分与したくない場合でも、しない選択肢を取ることが可能です。
離婚時に財産分与しない方法は、以下のとおりです。
- 財産分与しないのを夫婦ともに合意する
- 特有財産を主張する
- 借金による負担を主張する
- 相手の不貞行為やDVなどを理由での離婚を主張する
離婚に伴う財産分与を行わないのを夫婦ともに合意していれば、財産分与せずに離婚できます。
独身時代に得た財産は特有財産に該当しますが、区別がはっきりしなければ、特有財産であるのを主張するために、証明責任を負わなければいけません。
また、財産分与にはローンなどの借金もマイナス財産として含まれるため、財産分与したくないなら、借金の負担を主張しましょう。
相手の不貞行為やDVが原因で離婚する場合は、慰謝料の請求で財産分与と相殺するケースもあります。
財産分与すると不利な立場だと、財産を隠したり、離婚前に財産を使ったりすれば、財産分与せずに住むと考える方がいるでしょう。
財産を隠そうとする際、調停や裁判でイメージが悪くなったり、相手から損害賠償請求されたりするリスクがあります。
財産分与する前に財産を使い尽くしてしまうと、不当浪費とみなされ、使った財産を差し引いて分与する手段が判断されるでしょう。
離婚時に財産分与したくないなら、財産分与しなくても良いかまず夫婦間で話し合って、意見が食い違うなら調停や裁判で決めましょう。
離婚時に財産分与をしない場合の対処法
離婚時に財産分与をしない場合の対処法が、以下のとおりです。
- 離婚協議書を作成する
- 離婚条件に財産分与の放棄を加える
財産文書した方が円満に離婚できるケースが多い中、相手の借金などの関係で財産分与しない方が良いケースもあります。
財産分与しないときは、以下の方法で対処しましょう。
離婚協議書を作成する
離婚協議書は、離婚において夫婦間で取り決めたルールを記載する文書です。
離婚協議書には財産分与をしない旨を記載しておくと、公的の場で効果が発揮されます。
公正証書にすると、公証人が作成する文書になるので、より高い証明力を実現できます。
離婚条件に財産分与の放棄を加える
相手が離婚を強く希望している場合、離婚条件に財産分与をしないのを加えるのも1つの手です。
相手がなかなか財産分与の放棄に合意しなければ、専門的な知識を得たり、弁護士による交渉を検討したりする必要があります。
離婚の調停や裁判が完了するまで数年かかるケースがありますが、どうしても財産分与しなくない場合は、粘り強く主張し続けるのがポイントです。
離婚に伴う財産分与の種類
財産分与を行う場合、以下の3種類の分与方法に基づいて分配が実施されます。
- 清算的財産分与
- 扶養的財産分与
- 慰謝料的財産分与
ここからは、上記3つの財産分与の特性について解説します。
清算的財産分与
清算的財産分与は離婚時の財産分与で最も一般的な形式です。
この方法では、夫婦が婚姻期間中に築いた財産を、それぞれの貢献度に応じて分配します。
たとえば、専業主婦(夫)が家事に専念していた場合も、その労働は財産形成に寄与したとみなされ、財産分与の対象となります。
さらに、離婚原因を作った有責配偶者も、この形式で財産分与を請求することが可能です。
なお、分配する財産は、必ず均等になるように分配することを原則としています。
扶養的財産分与
扶養的財産分与は、経済的な困窮が予測される配偶者を扶養する目的で行われます。
例えば、病気で働けない状態や専業主婦(夫)で今後の収入が不透明、高齢で就労が難しい場合などが該当します。
この方法では、経済的に余裕がある配偶者が、相手に対して生活費を一定期間支払う形で扶養を行います。
慰謝料的財産分与
慰謝料的財産分与は、不倫やDVなど離婚原因を作った配偶者が、慰謝料の意味も含めて行う方法です。
この分与では金銭だけでなく不動産や株式など、金銭以外の資産による支払いも可能です。
慰謝料的財産分与は、離婚成立後2年以内に請求する必要があり、一般的な慰謝料請求の3年間とは異なります。
なお、財産分与においては基本的に贈与税は発生しませんが、一方が過度に多額の財産を受け取る場合には贈与税が課される可能性があるので注意しましょう。
離婚に伴う財産分与の対象になるものとならないもの
離婚時に行う財産分与には、対象になるものとならないものがあります。
ここでは、財産分与の対象になるものとならないものについてそれぞれ紹介します。
財産分与の対象になるもの
離婚に際して分与される「共有財産」には、夫婦が結婚中に共同で築いたさまざまな資産が含まれます。
- 現金・預貯金
- 生命保険(特に積立型)
- 株券や債券などの有価証券
- 一戸建て、マンション、土地などの不動産
- 自動車などの動産
- 年金、退職金など
上記6種類の資産は夫婦が協力して築いたものと見なされ、離婚時に分割されます。
「マイナスの財産」も財産分与の対象になる
離婚における財産分与では、マイナスの財産も考慮されます。
具体的には、住宅ローンや教育ローンの残債、クレジットカードの残高、未払いの諸費用、車購入ローンの残債などです。
これらは結婚生活のために生じた共同債務と見なされ、分与の対象になります。
ただし、一方の配偶者が個人的にギャンブルや浪費で作った借金は共有財産に含まれず、分与されません。
プラスの財産がマイナスの財産を上回る場合、プラスの財産からマイナス分を差し引いた残りが分割されるのが一般的です。
このように、離婚に伴う財産分与は、プラスの資産だけでなく、負債の側面も考慮する必要がある複雑なプロセスです。
財産分与の対象にならないもの
一方、「特有財産」と呼ばれるものは財産分与の対象外となります。
具体的には、独身時代に蓄えた貯金、結婚時に持参した嫁入り道具、どちらかの親から相続した遺産、別居後に獲得した財産などです。
個人が独自に所有する財産とみなされるため、離婚時の財産分与においては考慮されません。
離婚に伴う財産分与を適切かつ公平に行う上で、重要な役割を果たします。
離婚時の財産分与でよくあるトラブル事例
離婚時の財産分与でよくあるトラブル事例は、以下のとおりです。
- 共有財産を隠している
- 財産分与を拒否された
- 特有財産と共有財産が曖昧になっている
スムーズに財産分与の手続きを進めるために、起こり得るトラブルを把握して、しっかり備えましょう。
事例1)共有財産を隠している
相手が共有財産を隠している場合、個人名義の銀行口座やネット銀行の口座、貸金庫などで現金を隠蔽しようとしているケースが多いです。
銀行口座が明らかになっていると、取引履歴の開示を行って不自然か所を追求すれば、共有財産の発見ができます。
しかし、口座の取引履歴の開示は、弁護士照会によって確認する必要があります。
支店名まで明らかになっていないと、口座の取引履歴の開示ができないので注意しましょう。
弁護士照会でも開示できなかった場合、裁判所に調査嘱託を申し立てる必要があります。
ただし、明確な理由がなければ裁判所から許可が下りないため、スムーズに手続きを進めるためにも弁護士に依頼するのがおすすめです。
事例2)財産分与を拒否された
離婚時に財産分与しようとしても、相手に拒否されるケースがあります。
ただし、民法第768条により、原則離婚後2年以内は財産分与を拒否できないとされています。
財産分与を拒否された際は、法律により拒否できない旨を伝えましょう。
離婚後2年以降も、隠し財産が発覚したり任意で双方の合意のもと財産分与したりするなら、共有財産を分けられます。
事例3)特有財産と共有財産が曖昧になっている
夫婦間で特有財産と共有財産の認識が曖昧になっていると、財産分与でトラブルにつながる恐れがあります。
共有財産と思っていたものを特有財産と主張するなら、特有財産であるのを証明する必要があり、証拠を差し出さなければいけません。
共有財産と認識していた側は、基本的に何もする必要はありません。
特有財産であるのを立証できなければ、共有財産として扱われるのが一般的です。
離婚時の財産分与のトラブルを防ぐ方法
離婚時の財産分与のトラブルを防ぐ方法は、以下のとおりです。
- 共有財産を平等に分ける
- 共有財産をリスト化する
- 各財産の金額を明確にする
- 離婚前に税金の問題を把握する
離婚に伴う財産分与ではトラブルが起こる可能性があるので、未然に防ぐためのポイントを押さえましょう。
共有財産を平等に分ける
共有財産を平等に分ける際、不動産だと現在の市場価値を調査した上で、適切に財産分与する必要があります。
自分自身で調査するのが難しいなら、専門家に依頼するのもおすすめです。
財産分与の方法には、現物分割、換価分割、代償分割があるので、財産の形態に応じて適切な方法を選びましょう。
共有財産をリスト化する
共有財産を分ける前に、夫婦の共有財産をリストアップします。
財産分与の対象となるのは、現金や預貯金、保険や不動産、生命保険、株式、債権、退職金などです。
共有財産をリスト化する際、住宅ローンや自動車ローンなどのマイナスの財産も含めましょう。
目に見える形で共有財産を把握しておけば、離婚前に財産分与を済ませられ、お互いに心機一転して新しい生活を迎えられるでしょう。
各財産の金額を明確にする
共有財産をリスト化したら、財産ごとに適正な評価額を算出します。
| 財産 | 算出方法 |
| 預貯金 | 残高証明書や通帳 |
| 不動産 | 不動産会社の査定や固定資産税評価額 |
| 自動車 | 買取業者の査定や中古車相場 |
| 株・投資信託 | 証券会社の評価額 |
| 退職金 | 勤務先の支給予定額 |
財産の評価額が不透明だと揉めやすいため、公正な査定を依頼するのがポイントです。
財産一覧表を作成してお互いが確認できるようにしたり、合意内容を財産分与契約書にまとめたりしましょう。
公正証書の作成なら弁護士や司法書士、不動産の適正評価なら不動産鑑定士、金融資産の分配プランならファイナンシャルプランナーに相談するのがおすすめです。
公正証書にしておくと、後から財産分与を撤回したいといわれるリスクを回避できます。
離婚前に税金の問題を把握する
離婚に伴う財産分与では、手続きする前に税金の問題を把握しておくのがポイントです。
夫婦間での財産分与は原則贈与税はかかりませんが、分与の額が不公平に偏っている場合だと、贈与とみなされて贈与税がかかる可能性があります。
不動産の財産分与では、売却時に譲渡所得税が発生します。
住宅などの不動産を財産分与として渡すだけなら税金はかかりませんが、受け取った側がその後不動産を売却すると、譲渡所得税が発生するので把握しておきましょう。
独学で問題を把握するのが不安な場合は、税理士や弁護士、司法書士にサポートしてもらうのがポイントです。
財産分与の前に不動産を査定に出した方が良い理由
不動産の価値は、専門家の判断を仰がなければ正確に算出するのは難しいです。
まず、基本的に不動産の価値は築年数の経過によって年々下がっていきます。
更に経済状況や周辺環境の変化などの様々な要因によって不動産の時価は変化してします。
特に近年では、経済状況の変化が不動産価格に大きな影響を及ぼしています。
例えばリーマンショックや東日本大震災の直後に購入した物件が、オリンピック特需によって築10年時に購入時の価値を超えるという事例も珍しくありませんでした。
加えて2020年に新型コロナウィルスが世界的に流行したことで、再び相場が下がる可能性も出てきています。
不動産価格に影響する要因は逐一変化しているので、専門家に頼まなければ自力で今の価値を知るのは難しいのです。
財産分与の前に不動産一括査定を利用しよう
家の評価額を知るためには不動産会社へ査定を依頼するのがおすすめですが、査定価格はピンキリなので、必ず複数社の査定結果を見比べる必要があります。
複数社に査定依頼をするのは時間がかかりますが、一括査定サイトを利用すればスムーズに依頼が可能です。
申込に要する時間はわずか60秒ほど。価格だけ知りたい方でも完全無料で利用できます。
財産分与を意識した段階で、お早目に利用することをおすすめします。
不動産の財産分与を行うケースは主に2通り
不動産の財産分与を行うケースは、主に以下の2通りです。
- 離婚時に分与する
- 相続時に分与する
どのパターンに当てはまるかによって、方法等に違いが生じます。
離婚時に不動産を財産分与するケース
夫婦共同で購入し、暮らしていた住まいは離婚時に財産分与の対象になります。
片方が物件の所有権を譲り受けて住み続けるケースもありますが、争点になってくるのが住宅ローンの存在です。
優位的に財産を与えられたほうが残債を継続的に返済していくと、トラブルの種を離婚後に残してしまったのとほぼ同じです。
片方だけ継続的に返済を行うのは経済的・精神的にも大きな負担となるだけではなく、もう片方からすればキッチリ完済してもらえる確証のないまま不安を残して生活するようになります。
トラブルを未然に避けるために、離婚時に不動産を売り、代金を分与してそれぞれ新生活を迎えるのがおすすめです。
相続時に不動産を財産分与するケース
親の物件を2人以上の兄弟が相続する場合、基本的に権利を均等に分与されます。
不動産は1件しかありませんが、不動産の所有権を分割したという考え方です。
不動産の財産分与は換価分割という考え方で行われる
財産の中では、文字通り物理的に均等分与できるものもあります。
しかし、不動産は物理的に分割することができません。
そのため、遺産トラブルを引き起こす大きな要因となる可能性が大きいです。
では、不動産はどう財産分与をするかというと、換価分割という考え方に基づいておこなわれます。
換価分割とは、財産を一旦価格に換算した上で、財産分与をする方法です。
- 2,000万円の物件を4人で相続した場合:1人につき500万円分(25%)の権利が分与される
- 2,000万円・4人で相続した物件を売却した場合:1人につき500万円 (25%)ずつ取得をする
この方法によって、不動産が物理的に分割できなかったとしても、財産分与ができます。
代償分割によって財産分与することも可能
不動産の財産分与は換価分割の他に、代償分割という方法があります。
例えば、A・B・C・Dの4人のうちAが2,000万円の物件の権利を100%取得したとします。
この場合、分割された権利の割合は以下のとおりです。
- A :100%
- B・C・D :各0%
Aが物件を委譲せず、B・C・Dに現金500万円ずつ譲渡すると、以下のようになります。
- A :25%(2,000万円-1,500万円)
- B・C・D :各25%(500万円)
いびつな形にも見えますが、これでも4人が均等に財産分与できます。
財産分与をする際の状況はそれぞれ異なりますが、この考え方を持つことで幅広いケースに対応が可能です。
不動産を財産分与する流れ
離婚が正式に決定すれば、これまで築き上げてきた財産の分配を夫婦間で執り行います。
財産分与を行うときの大まかな流れは、以下のとおりです。
- 不動産の名義確認
- ローン契約の名義と残債
- 不動産価格の査定
- 特有財産の確認
- 査定額を元に話し合い
手順1】不動産の名義確認
財産分与の割合が最も大きい不動産を分配する場合、手始めに不動産の所有権がどっちの名義になっているかを確認します。
多くの場合が夫名義になっていますが、中には夫婦共有名義、夫婦いずれかの親族名義になっているなど様々なケースが想定されます。
また不動産の名義が誰なのか分からないという場合は、登記簿謄本(登記事項証明書)を取得して確認しましょう。
登記簿謄本は、法務局に出向いて直接頂くか、郵送やオンラインで取得できます。
なお、該当する不動産の管轄外の法務局でも登記簿謄本の取得は可能です。
手順2】ローン契約の名義と残債
2目は、住宅ローンやカーローンなどの契約名義とローン残債の確認です。
ローンの残債次第で、これから行う財産分与の結果が大きく変わります。
例えば、所有する不動産の名義と組んでいるローンの名義が異なる場合、分与上夫婦の共有財産に該当しても、ローンの名義が単独であるケースがあります。
この場合は、分与割合を決める際に大きく影響します。
また、ローン契約の名義と残債の確認を行うときは、ローンの連帯保証人の確認も併せて行いましよう。
手順3】不動産価格の査定
3つ目は、不動産価格の査定です。
不動産価格は、株式やFXのように浮き沈みが激しいわけではありませんが、築年数やその時の経済状況の影響を受けて価格が高騰したり、低落したりします。
不動産を財産分与する場合は、査定によって明記された金額を基に分与額を決定します。
手順4】特有財産の確認
特有財産とは、婚姻関係に至る前に所有していた財産や夫婦の協力とは無関係で得た財産などを指します
例えば、所有している不動産を購入するとき、片方が婚姻前に貯めたお金を使用していたり、片方の親・親族からの援助があった場合は、使用した金額分を差し引いて分与額を算出します。
手順5】査定額を元に話し合い
不動産の査定額を明確化したら、ローン残債から査定額を差し引いたオーバーローンかアンダーローンかを確認します。
オーバーローンとは、ローン残債に対して査定金額が低い場合を指し、アンダーローンはローン残債に対して査定金額が高い場合を指します。
特にオーバーローンの場合は、売却額とローン不足分を自己資金で完済するか任意売却で今後も払い続けるかを決める必要があります。
一般的にオーバーローンの場合は、財産分与をせず、ローン名義の方が今後も払い続けるケースが多いです。
とはいえ、これらの事情を踏まえて共有財産をどう分配するか、片方がこれからも住み続けるのかなど詳細に話し合いましょう。
離婚のために不動産を財産分与する方法
分配割合が大きい不動産を財産分与する場合は、売却して現金化する方法が一般的です。
不動産を売却して財産分与する方法は、以下のとおりです。
- 高値で売却するなら仲介
- 即現金化を行うなら業者買取
- オーバーローンの時は任意売却
- 片方が不動産に住み続けてもう片方に現金を支払う
様々な売却方法があるため、住宅ローンの残高や財産分与の方法などに応じて、適切な方法を選びましょう。
高値で売却するなら仲介
一般的な売却方法にして、高値で不動産が売却できる可能性を秘めているのが仲介による売却方法です。
仲介による売却方法は、媒介契約を締結した不動産会社に仲介を依頼して個人などに物件を売買する方法です。
仲介売買は、査定によって算出された価格に近い価格で売却ができるメリットがあります。
しかし、物件購入を検討する買い手が現れるまで必ず時間がかかるものです。
売却にかける時間に余裕があれば、仲介売却で物件売買を進めてみましょう。
即現金化を行うなら業者買取
すぐに不動産を現金化したい場合は、業者買取がおすすめです。
買取は、不動産会社に直接買い取ってもらう方法で、査定によって三種刺された金額に納得できれば最短1週間以内に現金が手元に入ります。
ただし、買取価格は、相場価格よりも安くなるケースが多いです。
ハウスクリーニングやリフォームを行う必要がない上、売却後に瑕疵が見つかっても損害賠償や契約解除を受ける契約不適合責任を背負いません。
オーバーローンの時は任意売却
任意売却は、ローン残債に対して査定金額が低い状態(オーバーローン)の時に利用できる売却方法です。
売却の時、融資を受けている金融機関の合意が得られれば、仲介売買と同じ手法で物件を売却できるうえ、出た資金をローン返済に充てられます。
ただし金融機関側にとって、売却資金で返済した後のローン残債は無担保状態になるので、必ず承認してくれるとは限りません。
夫(妻)が不動産に住み続けて妻(夫)に現金を支払う
売却以外の方法を選ぶ場合は、片方が不動産に住み続け、もう片方に不動産の見込み価値の半分相当の現金を支払うという方法を選ぶのがいいでしょう。
住む場所を変える必要がないため、子供がいる場合はその生活環境を維持できる点が大きなメリットです。
しかし、住宅ローンの支払い責任などが複雑になる可能性があり、特に共有名義だと所有権の変更や住宅ローンの名義変更など、多くの手続きが必要になります。
現金での支払いが必要となるため、資金計画を慎重に立てる必要があります。
ローンあり不動産を財産分与するときの計算方法
住宅ローンが残っている不動産を財産分与する場合、以下のケースが考えられます。
- ローン残高が評価額より多い
- 結婚前に一部を支払っている
- 別居後に住宅ローンを支払っている
上記の各ケースの計算方法を大まかに紹介するので、自身の状況に該当するケースをぜひ参考にしてください。
ローン残高が評価額より多い
住宅ローンの残高が評価額よりも高いと、マイナス財産として計上されます。
不動産以外の共有財産がプラスであれば、合算して住宅ローンの部分の控除が可能です。
夫の財産として不動産が4,000万円、住宅ローンが5,000万円、預貯金が2,000万円、妻には財産がない場合の計算方法は、以下のとおりです。
4,000万円(不動産)ー5,000万円(住宅ローン)+2,000万円=1,000万円
1,000万円を夫婦で500万円ずつ分ける
マイナス財産を他の共有財産と合わせて計上しても、プラスの財産が残らなければ、財産分与は行われません。
結婚前に一部を支払っている
結婚前に支払っている住宅ローンの支払い部分は、特有財産として計上され、支払った方が一部を単独で取得します。
不動産が5,000万円、住宅ローンの残高が3,000万円、2,000万年の返済済みのうち500万円を結婚前に支払った場合の計算方法は、以下のとおりです。
5,000万円(不動産)ー3,000万円(住宅ローン)ー500万円(結婚前に支払った分)=1,500万円
1,500万円を夫婦で750万円ずつ分ける
ただし、不動産の時価を購入時の価格と同じに設定しているため、時価によって前後します。
別居後に住宅ローンを支払っている
別居した後も住宅ローンを支払っている場合は、一部は特有財産として計上され、財産分与の対象にならないケースがほとんどです。
不動産の時価が3,000万円、別居時の住宅ローン残高が2,000万円、現在の住宅ローン残高が1,500万円の場合の計算方法は、以下のとおりです。
3,000万円(不動産)ー2,000万円(別居時の住宅ローン残高)=1,000万円
1,000万円を夫婦で500万円ずつ分ける
※2,000万円(別居時の住宅ローン残高)ー1,500万円(現在の住宅ローン残高)=500万円
別居後に支払った500万円は支払った方の特有財産
共有財産の計上で参考にする不動産の時価は、別居時のものを参考にします。
不動産は売却してから財産分与をした方が良い理由
不動産の財産分与は、建物を残したまま分割する方法(片方が物件を取得し、その価値の50%に相当する金額を支払う)と、建物を売って得た代金を分割する方法があります。
この2通りの方法のうち、不動産を売ってから財産分与をする方がメリットは大きいでしょう。
売却後に不動産を財産分与すべき理由は、以下のとおりです。
- 売却をする方が分割できる金額を大きくできる
- 物件・ローンを残さないことでその後のトラブルを避ける
不動産の売却後に財産分与する理由を把握した上で、財産分与の方法を決めましょう。
売却をする方が分割できる金額を大きくできる
物件を残して財産分与を行う場合、固定資産税評価額や不動産会社の査定額を参考にして金額を割り出して基準にします。
割り出した金額を時価(実勢価格)と言いますが、これは売却で得る金額(成約価格)とは必ずしもイコールではありません。
例えば、築年数が古い、敷地が広すぎるなどの要因でマイナス評価を受けた不動産を売らない場合、そこで評価額は確定します。
ただ、実際に売却する場合、売り出し価格は売主の意思で査定額よりも高く設定が可能です。
その後、掃除をして第一印象をアップしたり、マイナス評価を受けた部分を気にしない買主が現れたりしたら、そのまま査定額以上の金額で売れてしまいます。
財産分与の段階で価値がないと思われていた不動産でも、高く売ってくれる業者に頼めば金額のアップが可能です。
ただし、査定額より高く売り出すと「割高物件」というイメージを持たれ、売れ残る可能性も増えてしまうので、一括査定サイトを使って複数の業者をよく吟味する必要があります。
物件・ローンを残さないことでその後のトラブルを避ける
ローン付きの物件を片方が所有する場合、ローンを返済し続けるのが前提です。
万が一ローンの返済を放棄したなら、離婚後でも元配偶者が肩代わりしなければいけません。
物件・ローンを残しておくと、トラブルがいつ起こるか分かりません。
売却をしてトラブルの元をなくし、気持ちよく新生活をスタートさせたほうがお互いのためになります。
離婚時の財産分与で不動産を売るときの注意点
離婚時に行う財産分与の対象になる財産の中で最も大きな割合を占める不動産やマンションなどの不動産を売って、現金に換金する方法を選ばれる夫婦は多いです。
しかし、離婚を理由に不動産を売る時、様々なトラブルを招くことがあります。
円満な形で財産分与を進めるためにも、これから紹介するポイントをおさえて、不動産の売却を進めていきましょう。
- 住宅ローンの残債額を必ず確認すること
- 協議が決裂したら調停を申し出ること
- 同意なしで不動産を売られる可能性がある
- 不動産の基準価格をどうするか整理する
注意点1】住宅ローンの残債額を必ず確認すること
住宅ローンの残債がある場合、残りの金額が売却価格にどのように影響するか極めて重要です。
売却金額がローン残高を上回れば、超過分は分与の対象となります。
一方で、残債が売却価格を下回る場合は、不足分をどのように処理するか問題となります。
この状況下での分与には、特に慎重な計画と相互の合意が必要です。
また、売却による税金の影響も考慮する必要があり、税理士や不動産専門家のアドバイスを求めるのが賢明です。
注意点2】協議が決裂したら調停を申し出ること
離婚に伴う財産分与の協議が決裂した場合、家庭裁判所に調停を申し立てるのが一つの解決策となります。
調停では、中立的な調停委員が双方の主張を聞き、合意に至るための提案を行います。
しかし、調停には時間がかかるケースがあり、感情的な対立が激しい場合は調停がうまく機能しない事態も起こり得るでしょう。
裁判所での解決を求めるケースが一般的ですが、裁判は時間とコストがかかるため、可能な限り調停での解決を目指すのが望ましいです。
注意点3】同意なしで不動産を売られる可能性がある
共有財産である不動産を、片方の当事者が無断で売却するリスクも考慮しましょう。
勝手に売却されてしまう事態を避けるために、仮差押えの手続きが有効です。
仮差押えは、相手方が資産を勝手に売却や譲渡するのを防ぐ法的手段です。
登記があると、不動産の買主や仲介業者に対して、対象となる物件が係争中であるのが明示されます。
ただし、仮差押えには担保金が必要な場合が多く、手続きには法的な知識が求められるため、弁護士などの専門家と相談することが重要です。
注意点4】不動産の基準価格をどうするか整理する
財産分与時の不動産の取扱いとして重要なポイントの一つが、現在の不動産価格をいくらに設定するかという点です。
不動産の時価を判断する方法としては、不動産鑑定士に有料の鑑定を依頼する方法と、不動産会社に無料で査定を依頼する方法の2通りがあります。
| 比較項目 | 不動産鑑定 | 無料査定 |
|---|---|---|
| 評価主体 | 国家資格の不動産鑑定士 | 不動産会社の営業担当など |
| 法的根拠 | 鑑定評価に関する法律に基づく | 特に法的根拠なし(市場価格の分析に基づく) |
| 主な目的 | 証明資料(税務・裁判・会計)など | 売却提案・営業用 |
| 価格の信頼性 | 公的に通用する | 業者や物件によってばらつきあり |
| 費用 | 有料(数万〜数十万円) | 無料 |
夫婦間で係争中などのケースでなく、双方で金額に納得できるのであれば、無料の不動産査定の金額をベースとすることも可能です。
ただし、不動産会社の無料査定は金額にバラつきが起こりやすく、かつ売る側の”言い値”要素も含まれるので、鑑定評価より高値になりがちです。
こうした差異を調整するために、複数社の査定額の平均値を元にしたり、金額を少し下方修正したりすることもあります。
離婚後に夫(妻)が家やマンションに住み続けると住宅ローンはどうなる?
以下のように、離婚後に片方が住宅ローン継続中の家に住み続けるケースがあります。
- 住宅ローンの名義人が住むケース
- 住宅ローンの名義人ではない方が住むケース
- 夫婦で共有名義で住宅ローンを借りているケース
各ケースについて、どのようなメリットやデメリットがあるか解説します。
住宅ローンの名義人が住むケース
住宅ローンの名義人がそのままローンを支払いながら済むケースは、とてもシンプルな方法です。
しかし、片方が連帯保証人になっていると、支払いが滞ったときに支払いを行わなくてはいけません。
住宅ローンの名義人がそのまま済む場合は、連帯保証人の変更手続きを済ませるのがポイントです。
住宅ローンの名義人ではない方が住むケース
住宅ローンの名義人ではない方が住み、片方が支払いを続けるパターンは、子どもを引き取る側が住み続けるケースが多いです。
子どもにとって住まいの環境を変えずに生活を続けられるメリットがあります。
しかし、支払いが滞ると差し押さえされる恐れがあり、住み続けるのが難しくなってしまいます。
住宅ローンを支払っている本人が実際に住んでいなければ、支払いに対する責任が感じにくく、支払いが疎かになる可能性が高いです。
返済の滞りが不安な場合は、事前に公正証書で離婚時の住宅ローンの支払いについて条件を記載して作成しましょう。
夫婦で共有名義で住宅ローンを借りているケース
夫婦で共有名義で住宅ローンを借りて購入した場合、夫婦のどちらかが家を出て行くのは契約違反となるためできません。
夫婦どちらかの名義に変更しようとしても、共有名義だからこそ審査を通過して借りられたケースがほとんどなので、そもそもの契約内容が変わってしまいます。
どうしても住宅ローンを継続して住み続けたいなら、住宅ローンの借り換えを行う必要があります。
条件付きで不動産の財産分与が認められるケース
財産分与は、婚姻期間中に築いた財産を分配するときに行います。
「婚姻期間=結婚している状態」でのみ行われるものと思われがちですが、事実上の夫婦(内縁関係)である場合でも財産分与が行えます。
とはいえ、事実上の夫婦(内縁関係)である方が財産分与を行いには、特定の条件を満たしていなければいけません。
- 結婚の意思があったかどうか
- 一定期間以上の同居があったかどうか
上記2点をチェックして事実上の婚姻関係があると認められた場合、財産分与が成立します。
ほかにも、財産分与が認められるケースがあるので、財産分与の際はぜひ参考にしてください。
片方が死別してしまった
財産分与を検討している段階で片方が死別してしまった場合は、子供がいればそちらに相続をするという処理の仕方をします。
一方で子供がいない場合、離婚した元夫婦というのは遺産相続の関係ではありません。
そのため、財産分与は死亡した方の相続人に対して行使されます。
例えばA・Bの離婚後にBが死別した場合、AとBの相続人間で財産分与を行います。
死亡によって関係が解消されるケース
死亡によって婚姻関係が解消された場合、遺産を相続する形で処理されるので財産分与は行いません。
一方で、死亡によって内縁関係が解消された場合は財産分与できず、遺産相続もできない可能性があります。
ただし、内縁解消後に死亡すると、相続人に財産分与請求が可能です。
財産分与の請求期限に時効はないが早めにすべき理由
実は、財産分与の請求期限には時効がありません。
慰謝料には時効があるのですが、財産分与は長い話し合いが終わった時や思い出したときなど、いつでも請求が可能です。
ただし、「請求期限がない」という言い方には少しカラクリがあるので注意しましょう。
2年を過ぎても請求できない場合は任意での分与となる【除斥期間】
財産分与に請求期限はありませんが、強い法的根拠を持って請求ができるのは2年間と定められています。
2年以内であれば、相手が拒否をしたとしても、財産分与の請求が可能です。
ただし、2年を超えても財産分与の請求は可能ですが、相手側が応じてくれなければ話合いのテーブルに付けません。
そのため2年以内に請求できるに越したことはないですが、2年を過ぎたとしても調停・裁判によって除斥期間の延長が可能です。
財産分与の除斥期間2年を延長する方法
前述の通り、2年を過ぎると法的な財産分与の請求権を失効してしまいます。
原則、除斥期間の延長はできません。
相手側との話し合いでお互い納得し、財産分与を行う必要があります。
ただし、家庭裁判所に調停を申し出れば除斥期間の延長が可能です。
家庭裁判所に調停を申し出て除斥期間を延長する
家庭裁判所に調停を申し立てれば、双方で話し合いを行なって折り合いがついたら調停成立となります。
つまり、双方の話がまとまらずに2年を過ぎてしまった場合でも、調停を申し出れば納得がいくまで話し合いが可能です。
調停をしていくら話し合っても結論が出ない場合、裁判に移行します。
不動産の財産分与は子供も入れて計算する?
離婚で不動産の財産分与をする場合、基本的には子供を連れていく方もいかない方も同じく50%ずつで分け合います。
子供の養育をする方がお金もかかるので、多く取得しないとおかしいと感じる方も多いでしょう。
ただし、子供の養育の経済的問題は養育費によって解決します。
財産分与は結婚時に財産を共有していたか重要なので、離婚後の状況はあまり関係ありません。
状況によっては通常の財産分与(清算的財産分与)以外にも、双方の承諾があれば以下2種類の財産分与の方法を選べます。
| 特殊な財産分与の方法 | 内容 |
|---|---|
| 扶養的財産分与 | 片方が高齢・病気・育休などで就業が難しい際に、財産分与の配当を増やす |
| 慰謝料的財産分与 | 片方の不倫、DVなどが原因で離婚をした際に、もう片方の配分を増やす |
財産分与で相手が財産を隠していた時はどう対処する?
財産分与で相手が財産を隠していると、どう対処すべきか気になる方あいるでしょう。
財産分与は結婚当時の共同財産が対象になるので、本人同士が洗いざらい財産を出すしか方法はありません。
相手が財産を隠していれば、公正な財産分与ができなくなってしまいます。
そのため、以下の対処法で平等な財産分与を実現しましょう。
除斥期間内なら弁護士会照会制度が利用できる
除斥期間内なら、弁護士に依頼をして隠し財産を見つけられます。
弁護士会照会制度という仕組みで、事実関係を調べるために口座残高を調査するのが許されています。
ただし、弁護士は銀行の支店名まで知らないと調査ができないので、隠し口座があった場合は財産を見つけられません。
口座の存在は離婚前からチェックをしておくのがポイントです。
2年を過ぎた時の財産要求は根拠が必要
2年を過ぎた場合、民事裁判を起こして財産要求をする流れとなります。
ただし、民事裁判を起こすには証拠が必要です。
相手が財産を隠し持っているという証拠情報は、できるだけ多く取得しておきましょう。
不動産の財産分与に税金はかかる?
不動産の財産分与では、原則として贈与税はかかりません。
例えば離婚後に財産分与で片方が不動産に住み続ける場合も、贈与ではなく財産分与義務に基づく給付と見なされます。
財産分与で不動産を受け取った側には税金がかかる
一方、不動産を受け取った側には主に3種類の税金がかかります。(ケースによって種類の増減があります。)
- 登録免許税
- 不動産所得税
- 固定資産税
不動産を受け取った側にしかからず、双方で分担して納税するという決まりもありません。
ケースによっては贈与税・所得税がかかる
不動産の価値は一定ではなく、経済情勢や周辺環境の変化によって変わる可能性があります。
例えば、共同で購入した不動産が好況の煽りを受けてどんどん価値が上昇している場合は、実質的な贈与と見なされる可能性があります。
また、不動産の価値があまりに高いと、贈与と見なされる傾向にあります。
財産分与では不動産をどうするか優先的に考えよう
前述の通り、夫婦の共有資産に占める割合は、不動産が最も大きいです。
不動産の財産分与について優先的に考えると、トラブルを未然に防げます。
不動産の財産分与は様々な専門家が絡むので、売却するにしても時間がかかります。
早めに方針を決めて、早めの対応をしていくようにしましょう。
![GRO-BELラボ[株式会社グローベルス]](http://gro-bels.co.jp/labo/wp-content/uploads/2024/08/ラボ ロゴ-02-1.jpg)