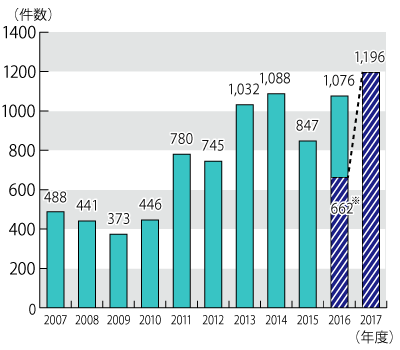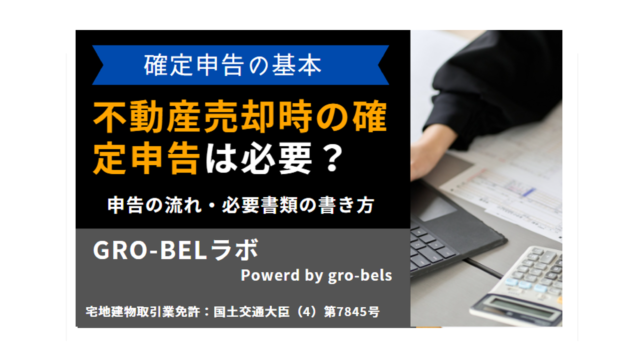不動産業界で大きく懸念されているのが、生産緑地の2022年問題です。
生産緑地の要件の変化によって不動産全体へ影響が及ぶことを懸念されていますが、現時点で問題の内容を詳しく理解している方はそこまで多くないと思います。
そこで今回は、生産緑地の2022年問題がなぜ注目されたのか、実際に何が起きたのか、そして2025年現在の影響や今後の見通しまでを、分かりやすく解説していきます。
- 生産緑地問題(2022年問題)とは?:生産緑地にかかる税を優遇する「生産緑地法」の期限が2022年であることから、生産緑地を手放す所有者が急増し、地価が急落することが懸念されていた
- 懸念されていたリスク:生産緑地は多くが首都圏・大都市圏にある上、国内の生産緑地は約1.2万ヘクタールという広大な面積になるため、それらが一斉に売り出されれば、地価への影響は必至と考えられていた
- 政府が実施した施策:10年間の税制優遇の延長を選べるようにしたことで、土地が大量に市場に出回るのを避けた
- 結果:生産緑地の所有者の多く(約9割)が税制優遇の延長を選択したことで、大きな問題は起こらなかった
そもそも「生産緑地問題(2022年問題)」とは?
「生産緑地問題」とは、1992年に一斉に指定された生産緑地の30年の営農義務が2022年に満了することにより、大量の農地が一斉に指定解除され、不動産市場に流れ込むことで地価が急落するのではないかと懸念された問題です。
生産緑地は本来、都市部に残された農地や緑地を保全し、税制上の優遇を受けつつ営農を続けるための制度でした。
生産緑地とみなすかどうかは申請式で、1992年の施行以来、主に税金の優遇を受ける目的で多数の申請があり、平成29年でも全国で12,972.5ヘクタールの生産緑地地区が残っています。
バブルが崩壊して間もない1992年は、バブル期に原野商法などで騙されて購入した土地や購入してすぐに価値が下落した土地を持て余す人も多く、こうした背景も生産緑地の増加を後押ししました。
| 年度 | 相談件数 |
|---|---|
| 2007 | 488 |
| 2008 | 441 |
| 2009 | 373 |
| 2010 | 446 |
| 2011 | 780 |
| 2012 | 745 |
| 2013 | 1,032 |
| 2014 | 10.88 |
| 2015 | 847 |
| 2016 | 1,076 |
| 2017 | 1,196 |
※2016年度同期件数(2016年12月31日までのPIO-NET登録分)
しかし、営農義務期間が終わる2022年に所有者が相次いで農地の解除や売却に動くことで供給過多に陥り、地価や資産価値への影響が広がるという「2022年問題」が不動産業界で大きな話題となったのです。
この問題は都市計画・税制・農業・相続といった多面的な要素が関係しており、特に首都圏や大都市圏に多くの生産緑地が集中していることから、全国的に注目されていました。
生産緑地問題(2022年問題)による地価暴落が起こらなかった理由
2022年の生産緑地問題では、多くの人が「土地の大量供給によって地価が暴落する」と予測していました。
ただし、実際には地価の暴落は特に起こらず、市場は安定したままとなりました。
結果的に懸念された問題が起こらなかった主な理由は下記の通りです。
理由1】特定生産緑地制度が創設された
特に大きな要因となったのが「特定生産緑地制度」の創設です。これは、平成29年6月15日に既存の生産緑地制度が改正されたものです。
- ○生産緑地の所有者等の意向を基に、市町村長は告示から30年経過するま
でに、生産緑地を特定生産緑地として指定できることになりました。- ○指定された場合、買取りの申出ができる時期が、「生産緑地地区の都市計画
の告示日から30年経過後」から、10年延期されます。- ○ 10年経過する前であれば、改めて所有者等の同意を得て、繰り返し10年
の延長ができます。- ○特定生産緑地の税制については、従来の生産緑地に措置されてきた税制が
継続されます。- ○特定生産緑地に指定しない場合は、買取りの申出をしない場合でも、従来の
税制措置が受けられなくなります。(激変緩和措置あり)- ○特定生産緑地の指定は、告示から30年経過するまでに行うこととされており、
30年経過後は特定生産緑地として指定できないことに注意して下さい。
上記の制度は要するに、もともと生産緑地として扱われた土地のうち所定の生産緑地に関しては、所有者の同意を得て生産緑地としての扱いを継続できるというものです。
つまり、生産緑地は基本的に2022年も、申請をすることで税制優遇などのメリットを受け続けることが出来るようになりました。
また、詳しくは後述しますが、生産緑地の利用制限が緩和されたことで活用の選択肢が増えたことも、所有者が「すぐに売却する必要がない」と判断する後押しとなりました。
理由2】不安に思って売却するケースが少なかった
上記の通り、特定生産緑地制度が創設されたことで、生産緑地をすぐに売却しなければいけないという認識はなくなりました。
しかし実際、生産緑地のオーナーは早くからこの件を楽観視しており、混乱に陥るようなケースはそこまで多くありませんでした。
生産緑地の2022年問題自体は以前から表面化していましたが、こうしたオーナーの姿勢も問題が大きくならなかった理由の1つです。
生産緑地として認められる条件
生産緑地として認められるためには、以下の4つの条件を満たしている必要があります。
- 農林漁業などの生産活動が営まれている、または公共施設の用地になっている
- 面積が500㎡(森林、水路、池沼などを含む)
- 生産活動の継続が可能である(日照などの条件が十分かどうか)
- 所有者以外の関係権利者全員が同意している
こちらの条件を満たしているかどうか、所轄の自治体が審査をして認められると生産緑地として認められます。
ただ、詳しくは後述しますがこの条件には解釈の余地も多く、問題も少なくありません。
生産緑地に指定されるメリット
メリット1】相続税の納税が猶予される
生産緑地に指定された土地を相続・遺贈する場合、取得者の相続税納税が猶予になります。
そのため、相続税対策として生産緑地の申請を利用する方も多いです。
ただ注意してほしいのは、納税猶予は控除・減税ではなくあくまで猶予という点です。そのため、生産緑地が解除された時点で、相続税は遡って課税されるようになります。
また、猶予期間の長さに応じた利子税も追加で課されるので、結果的に負担はより大きくなってしまいますが、相続税対策として初期負担を減らすには一定の効果があります。
メリット2】固定資産税が優遇される
従来より、農地は固定資産税が通常の宅地よりも優遇されますが、同様に生産緑地も固定資産税が優遇される仕組みとなります。
土地の分類によって固定資産税の優遇の度合いは変わりますが、生産緑地は農村部の一般農地ほどでなくても般緑地と同じ評価になるため、最大限課税を抑えることができます。
本来は宅地扱いになるはずの都市部の土地も税金が優遇されるのが、この生産緑地の最大の理由です。
土地の分類と固定資産税の優遇は、以下のようなイメージとなります。
| 土地の分類 | 税額のイメージ |
|---|---|
| 一般農地 | 約1,000円/10a |
| 生産緑地 | 数千円/10a |
| 一般市街化区域農地 | 数万円/10a |
| 特定市街化区域農地 | 数十万円/10a |
生産緑地に関する法律の改正と条件の変遷・2022年問題への対策の歴史
生産緑地法は元々は1972年に制定された法律ですが、1992年に新生産緑地法の制定がおこなわれてから、頻繁に法改正がおこなわれました。
| 年 | 内容 |
|---|---|
| 1992年 | 新生産緑地法の制定 |
| 2016年 | 都市農業振興計画の閣議決定 |
| 2017年 | 新生産緑地法の改正 |
| 2018年 | 田園住居地域の創設 |
| 2018年 | 都市農地賃借法の制定 |
1992年に新生産緑地法の制定がおこなわれ、従来指定が難しかった生産緑地の条件が緩和され、指定を受ける農地が一気に増加しました。
更に、2016年に都市計画振興計画の閣議決定がおこなわれ、生産緑地の意義が転換されました。
従来は都市拡大を段階的におこなうため、生産緑地のエリアは都市部に残しつつも、最終的に市街化を図る対象とみなされていました。
ただ時代の変遷により都市と緑の共存、環境保護が叫ばれるようになり、生産緑地は都市部に必要なものという認識に変わりました。
2017年の新生産緑地法改正のポイント
上記の中で特に重要なのが、2017年の新生産緑地法改正です。
これにより、以下の3点が大きく変わりました。
- 特定生産緑地の指定
- 面積の要件引下げ
- 行為制限の緩和
従来、生産緑地は30年の義務終了後に市町村へ買取申し出がありますが、これによって後述する2022年問題が発生しやすくなっていました。
特定生産緑地に指定された土地は買取申し出を10年延長できるので、短期間での大量売り出しを避けることができます。
また、生産緑地に指定される面積が500㎡以上から300㎡以上に引き下げられました。
こちらは小規模な土地の多い都市部で運用するために面積要件を適正化する目的がありました。
最後に紹介する大きな変更が、生産緑地でおこなわれる行為制限の緩和です。
従来は生産緑地=農地でしたが、改正によって農業生産の他に商品の製造・加工・販売施設やレストランなどを設置できるようになりました。
都市農地賃借法の制定により第三者に貸しやすくなった
次に重要なのが、2018年の都市農地賃借法の制定です。
これにより生産緑地の貸借条件が緩和され、第三者に貸し出しやすくなりました。
2022年問題の問題点は生産緑地の指定解除によって、大量の土地の売り出し・放棄が起こることでした。
生産緑地の賃借条件が緩和されても手放されることには変わりませんが、引き続き管理者が生まれるので、荒廃を防ぐことができます。
生産緑地の2022年問題以降の土地活用方法
現在が2020年なので、2022年の生産緑地解除までに膨大な準備時間が取れる訳ではありません。
ただ、今の状況を生かしつつ2022年問題に向けて対処する方法はいくつかあります。
- 生産緑地を解除して土地を売却する
- 生産緑地を解除して土地を有効活用する
生産緑地を解除して土地を売却する
生産緑地を解除して土地を売却する方法もあります。
これにより、固定資産税の支払いを避け、市街化区域内の土地であれば、宅地転用して住宅用地として売却することが可能になります。
ただし、土地を売却することで一時的な収益は得られますが、長期的な土地活用や収益化の機会を失うデメリットがあります。
また、納税猶予制度の適用を受けている場合は、さかのぼり課税の問題が発生する可能性もあります。
売却案としては、土地を宅地転用し住宅用地やアパート用地、高齢者施設用地として売却するのが一般的です。
生産緑地を解除して土地を有効活用する
生産緑地を解除し、土地を有効活用する方法は、収益化の可能性を秘めていますが、同時にリスクも伴います。
解除後のメリットとしては、農業からの収入に依存しなくなることや、宅地としての価値を活かした高い収益を得る機会があります。
特に市街化区域内の土地は、住宅用地や商業施設としての売却や開発が期待できます。
ただし、経営がうまくいかない場合、収益化どころか負債を抱えるリスクもあるので注意が必要です。
生産緑地問題による暴落は発生ししなかった
最初に2022年問題のリスクがささやかれた時には、2022年を機に大量の土地が叩き売られ、地価が大幅に下落することが予想されていました。
しかし、税制優遇措置の延長が選べるようになった結果、多くの土地所有者が延長を選択肢、結果的に地価の下落につながることはありませんでした。
こうした政策が効果的である以上、今後も生産緑地に関する大きな問題が発生する見込みは薄いと考えて良いでしょう。
![GRO-BELラボ[株式会社グローベルス]](http://gro-bels.co.jp/labo/wp-content/uploads/2024/08/ラボ ロゴ-02-1.jpg)