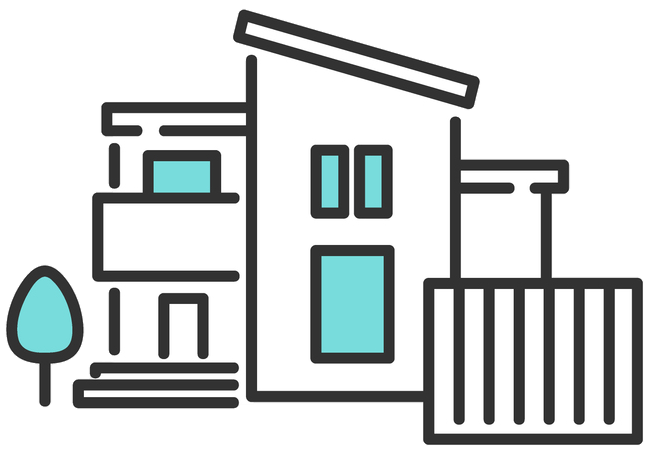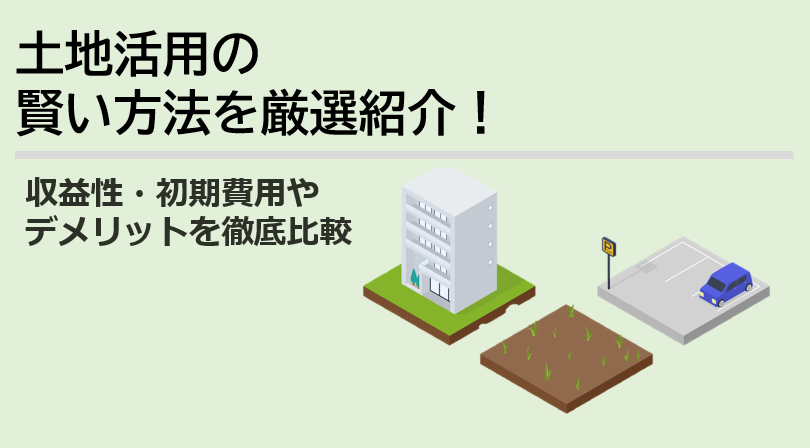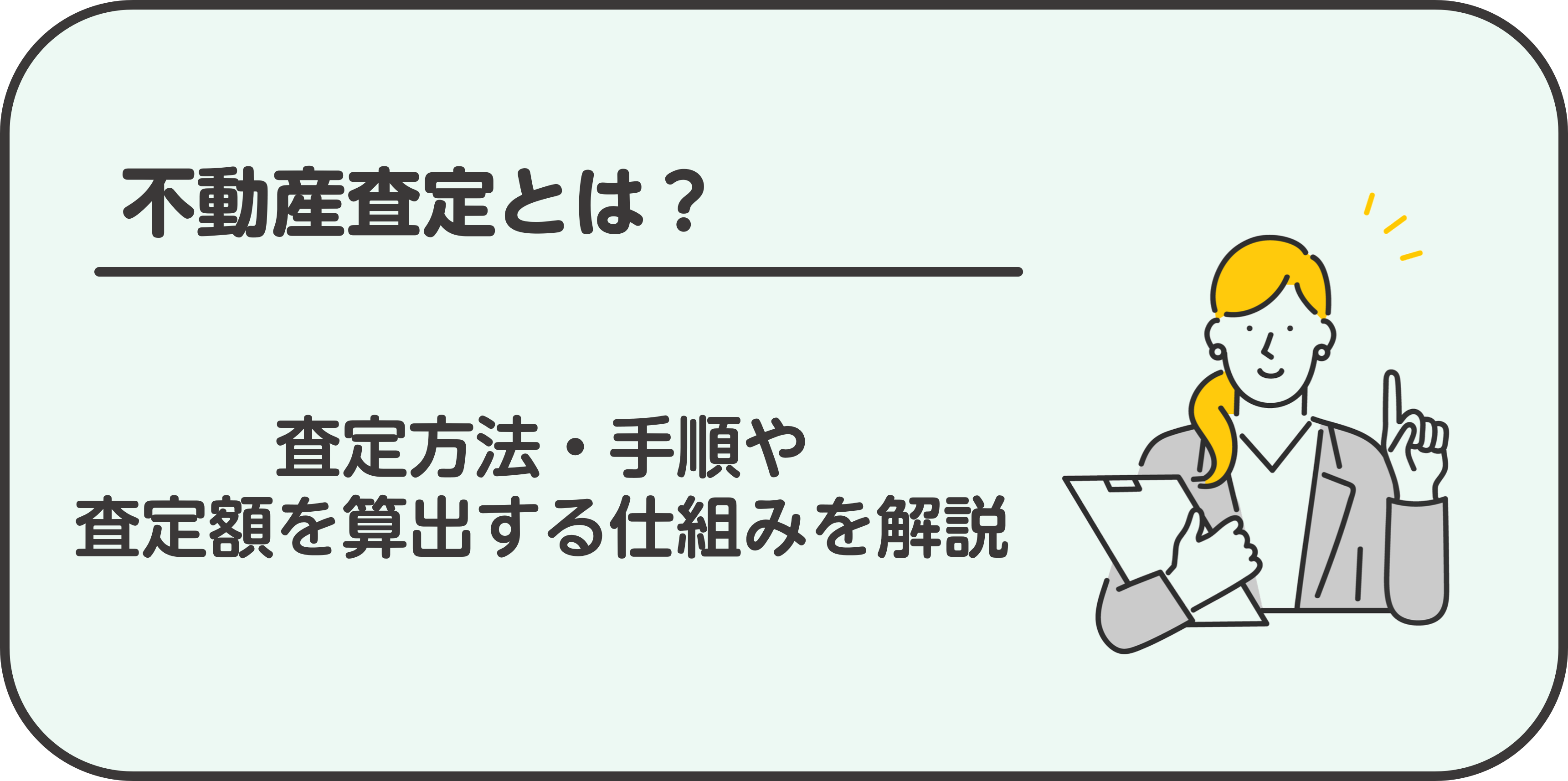不動産事業者様へ【無料掲載募集!】
不動産事業者様へ【無料掲載募集!】
不動産売却時の税金計算・確定申告では減価償却が重要!事業用・居住用の違いと計算方法を解説
- 本ページにはPRリンクが含まれます。
- 当サイトでは、アフィリエイトプログラムを利用し各事業者から委託を受け広告収益を得て運営しております。
不動産売却によって利益が出ると、譲渡所得税という税金がかかってしまいます。
物件の価格によって課税額は変わってきますが、100万円近くなることも多いので、注意をしましょう。
この税金は計算式が決まっており、事前に課税額のシミュレーションをしておくこともできるのですが、このときには減価償却費の計算が必要となります。
この記事では、そんな減価償却の内容から算出方法までを解説します。

減価償却の内容と仕組み
譲渡所得税の計算式は一定となっています。
不動産の取得費と売却費用を差し引いたものが譲渡所得であり、これに税率をかけて算出される税金です。
ただ、この取得費は、償却費を引いてから計算されます。
取得費とは、物件を購入したときにかかった費用のことであり、当時支払った仲介手数料やリフォーム費用なども含まれます。
購入額自体は含まないので注意しましょう。
取得費に含まれる費用
不動産の取得費に含まれる費用は、以下の通りです。
- 不動産を購入したときに納められた登録免許税・印紙税・不動産取得税などの税金
- 借主立ち退きのてみに支払った立ち退き料
- 土地の整地作業のために支払った費用
- 土地の測量費用
- 所有権確保のために訴訟をおこしたときの費用
- 当初から土地利用が目的だった場合の物件立て壊し、更地化の費用
- 不動産購入のために借り入れた資金の利子のうち、引き渡し日までに支払った費用
- 複数の不動産を契約していたときに、ほかの取得を辞退したことによる違約金
上記のようなものが取得費となりますが、要するに購入時にかかった費用はほとんど取得費として計算されるということです。
どのような購入の方法をとったかによっても費用は大きく変わりますが、取得費の相場としてはだいたい100万円前後となります。
譲渡所得税は取得費-減価償却費で求める
引き渡し後に税金を支払うときには、この合計から償却費を引いていきます。
譲渡所得を算出するときには取得費を使いますが,取得費は購入当時の費用そのままではなく、築年数に応じて費用を差し引いた金額となります。
この、築年数によって減少した価値を差し引くことを減価償却といいます。
土地には加齢による劣化という概念がないので、減価償却は建物にだけ適用されます。
定額法と定率法の違い
減価償却は、定額法と定率法という2つの計算法が利用されます。
定額法は、減価償却費を毎年同額に設定する方法です。
一方、定率法は、固定資産の取得年から、少しずつ減価償却費が減少していく方法です。
ここからは、それぞれの計算式について紹介します。
定額法の例
- 購入価格:800万円
- 耐用年数:15年
- 定額返済率:1/15=約6.67%
- 1年間の減価償却費:800万円×6.67%=約53.36万円
この計算式の場合、毎年約53.36万円が減価償却される計算になります。
定率法の例
定額法の例と同様に、購入価格800万円、耐用年数15年とすると、初年度の減価償却費は下記の通りとなります。
- 比率:6.67%×2=約13.34%
- 初年度の減価償却費:800万円×13.34%=約106.72万円
この場合、初年度は約106.72万円で、そこから減価償却費は減少していき、合計は定額法で計算した値と同額になります。
どちらの方法を選択するかは、企業戦略・資金計画などに基づいて選択されます。
事業用不動産の減価償却方法
事業用不動産の減価償却には定額法が使用され、取得年月によって償却率が異なります。
平成19年3月31日以前に取得した資産の定額法は下記の通りです。
- 計算方法:減価償却費=(建物購入価額−残存価額)×回収率×業務に提供された月数/12
- 残存価額:取得価額の10%
- 返済率: 耐用年数に応じた旧定額法返済率
- 業務に提供された月数: 月単位で計算
平成19年4月1日以降に取得した資産の定額法は、下記が適用されます。
- 計算方法:減価償却費=建物購入価額×回収率×業務に提供された月数/12
- 返済率: 新定額法返済率
旧定額法では、耐用年数16年の返済率は0.062、耐用年数30年は0.034です。新定額法では、耐用年数16年で0.063、耐用年数30年で0.034となります。
注意点として、業務に提供された月数は、とりあえず1日でもあれば1ヶ月として計算されます。
還元計算では、月単位での計算が重要で、1日でも利用された場合は1ヶ月とカウントされるため、計算時に注意が必要です。
これらの点を踏まえると、事業用不動産の減価償却費においては、取得時期によって異なる償却率を適用し、建物の購入価額と業務に供される期間に基づいて償却費を計算することが重要です。
取得年次別の事業用不動産の減価償却
事業用不動産の減価償却方法は、過去に何度も補正を経て変更されています。これにより、取得時期によって異なる償却方法が適用されることになりました。
- 平成10年4月1日以降の取得:定額法に限定され、償還可能限度額や残存価額の概念が廃止され、耐用年数経過時に1円まで償還が可能になりました。
- 平成19年4月1日以降の取得:定額法または定率法を選択でき、定率法解消率として250%定率法が導入されました。
- 平成24年4月1日以降の取得: 定率法解消率が見直され、200%定率法が開始されました。
- 平成28年4月1日以降の取得:建物付属設備および構築物の解除について、定額法が廃止され、定額法のみとなりました。
平成10年3月31日以前および平成28年3月31日以前に取得した事業用不動産については、定額法と定額法いずれか選択できます。
これらの変更は、事業用不動産の償還計画に大きな影響を与えており、特に取得時期による償還方法の選択肢の変更は、適切な適正計画を立てる上で重要なポイントとなっております。
居住用不動産の減価償却費の計算方法
ここからは、実際に減価償却費はどのように計算するのかを紹介していきます。
なお、償却費は不動産が事業用か、非事業用かによって大きくかわります。
事業用とは、不動産を事務所や運用目的で利用をしたもののことで、非事業用は主に事業目的で利用されたものです。
ここでは、主に非事業用に焦点をあてていきます。
また、以前は定率法という方法がとられていましたが、1999年4月1日に取得した建物や、それ以前に購入されたものでも特別な届け出がない場合は、定額法によって算出されます。
ここでは、定額法の減価償却費を紹介します。
不動産の減価償却率は構造により異なる
償却率は、木造の場合は0.031%、軽量鉄骨の場合は0.025%、鉄筋コンクリートの場合は0.015%となります。
減価償却とは、不動産が故意ではない自然な劣化による価値の減少を考慮してカバーするものです。
そのため、木造のほうが償却率は高く、逆に鉄筋コンクリート造の場合は償却率が低くなっています。
ただ、物件にはそれぞれ耐年数があり、これを超えると償却は適用されないので注意が必要です。
不動産種別ごとの耐年数
耐年数、築年数は物件の売却代金を考慮する上で必要です。
しかし、それだけではなく、減価償却をふくむさまざまな特例や税金控除の適用基準としても重要になります。
耐年数は、木造は22年、軽量鉄骨造は40年、鉄筋コンクリート造は 47年となっています。
しかし、この年数は売却が可能である最大限の年数であり、通常は築20年を超えると売却代金は大幅に減少してしまいます。
→木造住宅の耐用年数とは?減価償却・査定への影響をわかりやすく解説!
減価償却費の計算式とシミュレーション例
計算式は以下の通りとなります。
減価償却費=物件の取得費×0.9×償却率×経過年数(築年数)
経過年数が端数となっている場合は、6か月未満を切り捨て、6か月以上は切り上げられます。
ちなみに、減価償却費計算に関わる要素は、建物の構造によって以下のように変化します。
| 区分 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 金属造(肉厚4㎜超) | 金属造(肉厚3~4㎜) | 金属造(肉厚3㎜以下) | 木造・合成樹脂 | 木造モルタル造 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法定耐用年数 | 47年 | 34年 | 27年 | 19年 | 22年 | 20年 |
| 償却率 | 0.015 | 0.02 | 0.025 | 0.036 | 0.031 | 0.034 |
新築時は1,000万円だった木造建築を築10年で売る場合、以下のように計算します。
1,000万円×0.9×0.031×10年=279万円(減価償却費)
つまり、この場合の取得費は1,000万-279万=721万円となるわけです。
不動産売却時に利用できる特例や控除
譲渡所得税は不動産を売却した際にかかる税金です。
売却で得た所得の額によっては高額な課税になることもあります。
自ら居住する不動産を売却した際の譲渡所得税は負担が重くならないように設定されている特別控除や特別軽減税率があります。
以下にそれぞれの控除や特例を紹介します。
住宅ローン控除
売却益を新たな住宅の購入や改築に使った場合に適用される控除です。
具体的には、売却した不動産から得た利益を新たな住宅の取得費や改築費に充てた場合、その金額を譲渡所得から控除することができます。
ただし適用には一定の条件があり、新たに取得または改築した住宅を主たる生計を維持するための住宅として使用しなければなりません。
中小企業者等特例
中小企業者が所有する不動産を売却した場合、特定の条件下で売却益の一部が課税されない特例が適用されることがあります。
中小企業者が経済状況や事業計画により不動産を売却する際に、その売却益に対する課税負担を軽減するためのものです。
配偶者控除
配偶者控除は、配偶者がいる場合に適用される控除です。
配偶者の年収が一定額以下である場合、所得税の計算時に一定額を控除することができます。
これにより、所得税の負担を軽減することが可能です。
譲渡損失の繰越控除
不動産を売却した際に損失が発生した場合、その損失を繰り越して将来の所得税から控除することができます。
譲渡損失は、3年間繰り越して控除することが可能です。
この繰越控除を利用することで、将来発生する所得に対する税金の負担を軽減することが可能となります。
減価償却費で損をしないためのポイント
減価償却費の算出は、税金をシミュレーションするためには重要ですが、だからといって増額するために何か対策できるものでもありません。
購入時にかかる税金などの費用をすべて合計するとだいたい200万円前後となりますが、査定の低い業者と高い業者では300万円の差があるといわれているので、費用の心配をするよりも事前にしっかりと準備をし、適した業者へ査定を依頼することのほうが更に重視すべきなのです。
つまり、不動産売却ははじめにどんな準備をするかが最も重要ということです!
まずは正しく確定申告をしよう!
譲渡所得税の納付時には、確定申告をおこなう必要があります。
確定申告をする時期は売却した翌年の2月16日から3月15日までと決まっているので、税金計算をする以前にまずは所定の期間で確実に確定申告をする必要があります。
サラリーマンにとっては少し複雑な手続きですが、こちらにわかりやすく方法を掲載しているので、ぜひ参考にして下さい!
→不動産売却後の確定申告の流れ!申告時期から必要書類の書き方までわかりやすく解説